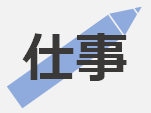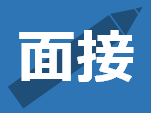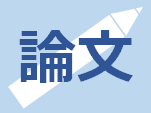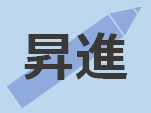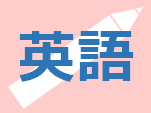会社で働くからには、いずれは昇進して課長になり部長になり、というようにマネジメント職に就いたほうが良いのでしょうか?
グイグイ出世して給料を上げて発言権を得て、、、ということに魅力を感じている人は昇進を目指すことも良いと思います。確かに、多くの日本の会社が、
給料=職種、成果
ではなく、
給料=役職、等級
です。昇進すれば給料が上がります。
その会社に居続ける限り、
その会社が倒産しない限り、
その会社に降格の制度がない限り、
より高い給料をもらい続けることは可能です。
しかし、これから終身雇用が崩壊へ進み、仕事にAIが導入され、定年退職から始まる余生が長くなる中、ひとつの会社で課長などマネジメント職を長く続けることにはデメリットもあります。
実務から離れ、その会社独自の文化や制度の中でマネジメントしていると、社内でのステータスは上がりますが、いわゆる「手に職」は身に付きません。
この記事では、平社員をずっと続けても、職業スキル、専門スキルを徹底的に磨くことで得られるメリットについて解説します。昇進出来なくても、決して悪いことばかりではないことを実感していただけると思います。
平社員を続ける5つのメリット
平社員、すなわち実務を担当するポジションです。それに対して課長などの管理職は、仕事が上手く回るように業務やスタッフを管理・監督し、事業方針を課業務に落とし込みます。もちろん、どちらのポジションも重要で、片方欠けてもダメです。
どちらのポジションにもメリットは様々あります。課長になれない、なりたくない、という人のために、平社員を続けるなら、次に挙げるメリットを十分に理解し、計画的に平社員を続けることをおすすめします。
専門知識をたくさん吸収できる
平社員として実務を続ける上では、必ずその分野の専門知識が必要になります。仕事を進めていく上で、必要な専門知識が欠けていれば、それを専門書やネット検索で調べて自分のものにすれば良いのです。
仕事のスキルは、実務とそれをバックアップする専門知識が加わることで飛躍的に上達します。
管理職になると、業務内容が組織の運営や労務管理などになり、その課の専門分野のお勉強を新たにしても、実務との相乗効果が図れず、スキルとしての定着は難しいです。管理職のほとんどは、平社員時代に培った知識と経験、地頭力で、部下と専門的な話をしている場合がほとんどです。
もし、スーパー平社員を目指すなら、その道では誰にも負けないほどの最新の専門知識を実務を通して習得すると良いでしょう。その分野であれば独立してもやっていける、くらいのスキルを磨ける時間が確保できるのも、平社員のメリットです。
やり遂げる苦労を実践できる
実務担当者は、ひとつ1つの業務を最後までやりとげなくてはなりません。終わった時の達成感は、平社員ならではです。
このやり遂げた感は、リーダーや管理職になるとほとんど味わうことが出来ません。ひたすらマネジメントを行う日々です。課やプロジェクト全体として達成感はあっても、メンバー達の実務貫徹の集大成です。
どんな職種であっても、時代と共に手法やツールが変わります。その時代の最新のやり方で、どの業務がどれくらいの難しさがあり、どれくらいの苦労が必要であるか実感できることは、大きな経験値となります。いずれ転職、独立した時、類似した業務を遂行する際、難易度や見通しが手に取るように分かります。直担当ならではの経験値です。
現場を知ることができる
どんなお仕事にも、全体を管理する側と現場のふたつがあります。平社員は多くの場合、現場サイドです。
例えば、メーカーでのケースを考えます。部品の製造を海外でおこなっている場合が多いです。品質保証や工程監査の目的でその製造会社を訪れることもありますが、その部品の実務担当者として海外出張出来るのも大きなメリットです。最新の技術を用いた製造工程を間近で見て、現地スタッフから様々なことを直接聞いて、、など、良いことだらけです。
新規の調達先を開拓するなどの大きな案件の場合には、課長級以上の人が行くこともありますが、大抵は、平社員です。
あくまで一例でしたが、このように現場の生の声、難しさ、苦労などを身に染みて体験できることは、後の大きな財産になります。海外出張に限らず、様々な実務を経験することで、自分の手を動かして達成する経験の引き出しが増えます。
リーダーのように人を動かして成果を出すことも大切ですが、いざ自分の手で何かをするというときに、実務経験の多さは、身を助けます。
実務経験は転職のときアピールになる
転職活動をする際、実務経験として様々な実績があると、アピールになります。
もちろん、係長や課長として部下をコントロールして実績をあげてきた経験もリーダーシップやマネジメント力として評価されます。しかし、あくまでその会社の仕組みの中で機能していた可能性もあり、そのスキルが著しく突出したものでない限り、他社でも評価されにくいものです。目に見える実績として残りにくいのもデメリットです。
その点、実務経験から来る専門知識やスキルは揺るぎないアピールポイントとなります。
「○○商品の△△モジュールの部分の開発設計を担当して製造工程を立ち上げて商品化」
→同じ業界であれば、そのプロセスでどのような要素があるか分かりますので、その実務を任せられると判断出来ます。
転職しようと考えたとき、職務経歴書に専門的な具体的アピールを書きやすいことは、実務経験から来ます。
もし、中小企業から大企業にステップアップしたいと考えた場合、中小企業のマネージャーから大企業のマネージャーとして転職するのは大変難しいです。中小企業でも、その個人のスキルから生み出される実務での実績は評価に値し、専門スキルを活用して即戦力として動ける、と判断されます。
極端な例を挙げます。早々と管理職になると、事務作業は秘書や庶務担当にお願いすることが多くなることがあり、エクセルやPowerPointすら満足に使えない人もいて、転職の土俵にすら乗れない悲惨な状況になります。
実務は副業や自営業に生かせる
何かを自分で始めたい、と副業や自営業を考える人は多いと思います。インターネットが普及して、自分で様々なことを出来る時代です。
こんなときに、平社員として実務経験が長いと、重宝します。マネージャー職が長いと、自分で手を動かして進める機会は、平社員時代に比べて格段に減ります。マネージャー職として人や労務を管理したり、上層部と部下の間で調整したり、といった業務は、自分で何かを始めるに当たってほとんど役には立ちません。
エクセルやPowerPointをはじめ、様々なツールを使って泥臭い実務を多くこなした経験は、副業するに当たり、スムーズに事をこなせるでしょう。
部長級や課長級で会社を止めて、自分で新しい仕事をはじめた人を何人も見たことはありますが、全ての人がマネジメント力ではなく個人の専門知識を生かしたものでした。筆者が見たのは、塾の開業、コンサルタント、芸術系、設計事務所など。そのような人達は意識が高く、マネジメント業務に追われながらも自分を見失わず、自己鍛練をしていたと考えられます。
このあと、まとめに入ります。
まとめ
平社員を続けること、課長になれないことは、決してネガティブなことではなく、考え方次第でとても将来性のあることです。是非とも前向きに捉えて自分の目指す形を定めてそこに向かって専門スキルを確立し、来るべき時に備えましょう。
マネージャーになると、ほんとに実務から離れてしまい、専門スキルを磨く機会が遠のき、マネジメントに徹する時間が多くなります。現場力を身に付ける時間が少なくなります。
将来多くの選択肢を残すためにも、平社員での時間を実のあるものにしましょう。
最後に蛇足ですが、この記事に共感して、バリバリ専門スキルを身に付け、現場に赴き、一人で何でもやって行けるような、意識の高い人をいつまでも平社員で置いておくような会社は無いかもしれません。この記事を最後まで読んでいる時点で、意識高い系、だと筆者は感じます。