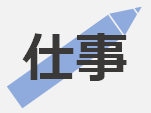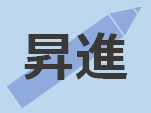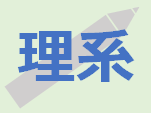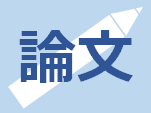現職の保育士・幼稚園教諭で、一般の企業への転職を考えている、という人は多いと思います。
理由はさまざまでしょう。
・不規則な労働スタイル
・サービス残業
・安い賃金
・良好でない人間関係
・就業規則の不備
・保護者とのトラブル
など。
この記事では、保育士・幼稚園教諭から一般の企業に転職するのにあたり、仕事の違いや、取るべきアクションで知っておくべきことを、徹底解説します。役立つ情報へのリンクも紹介しています。
まとめて「保育士」「保育園」「会社」と記述することにします。
保育園と会社の違い
保育園でも複数の園にまたがって組織的に統一した保育・教育方針で仕事を管理するところもありますが、多くの園が自園だけの小規模な運営です。会社はその点、多くの部門の社員で構成されています。
保育士を辞めて会社務めを考えている人は、個人経営や社員数人の零細企業を希望している、ということはないでしょうから、本記事での「会社」とは、数百人とか数千人規模の会社を想定した説明になっています。
では、保育園との比較での会社の主な特徴を挙げます。
組織が大きい
会社は、社員数が多いです。多くの会社機能が細分化されています。それによって、
・仕事を進める上で関わる人が多い
・おびただしい数のルール、方針が定められている
・専門性の異なる人がたくさんいる
・たくさんのことを学べる
・ほか仕事の部門に異動できる
・組織を健全に保つ活動がある
など、メリットともデメリットとも取れるようなたくさんの、保育園との違いがあります。それぞれのメリットとデメリットを挙げます。
■関わる人が多い
・メリット
仕事を分担できる。協力体制が確立されている場合が多い。
・デメリット
自分の考えだけで進められない。
■たくさんのルール、方針
・メリット
ルール、規定類、方針で統制されているため、変な社員はほとんどいない。リーダーひとりに振り回されることは稀。
・デメリット
ルールを知らないといけない。柔軟な対応には協議が必要。ルールを作る作業もある。
■専門性の異なる人がたくさん
・メリット
仕事で関わることで多くの知識を得られる。
・デメリット
知らないこと、難しいこともたくさん説明されるので、学び続ける覚悟、自分も専門性を高める努力が必要。
■たくさん学べる
・メリット
研修や教育、学習プログラムがたくさんあり、スキルアップできる。普段の業務で、経済の動きや仕組み、安全衛生、販売、財務など、会社を取り巻くさまざまな側面での情報が飛び交い、生きていく上での多くの知識を得られる。
・デメリット
たいていの場合、情報や届くメールが多く、取捨選択のセンスが必要。
■ほかの部門に異動
・メリット
今の仕事が合わない場合、社内でほかの部門に移る希望を出せる。転職なしで人間関係のリセットを図れる。
・デメリット
希望しなくてもほかの部門に異動させられることもある。
■組織の活性化の活動がある
・メリット
人間関係の悪化やギスギスした部門の雰囲気を是正する仕組みがあるため、快適に仕事ができる環境へ改善される。
・デメリット
問題抽出やそのための打ち合わせなど、仕事以外での取り組みが多く、やることが多岐にわたる。
メリット、デメリットのどちらと捉えるかは本人次第です。今の勤め先の保育園にも該当するものはあるかもしれませんが、社員数が多くなるほど、組織の統制のために、良くも悪くもたくさんのことが自分を取り巻きます。
![]()
品質、コスト、納期のすべてに敏感
会社は、良質な商品やサービスを、定められた日程の中で提供し、多くの利益を創出する、というミッションがあります。すべての会社が、品質、コスト、納期という3要素にとても敏感です。
コストダウンを推進するためだけの部門、全社の製品やサービス品質を統括する部門、生産日程管理をする部門、のような特化した部門もあるくらいです。全社員が品質、コスト、納期を常に意識した言動を求められます。
品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)の頭文字を取って、QCDといいます。近年は、環境保護の観点から、環境(Enviroment)にも配慮した取り組みが法的に義務化されてきたこともあり、EQCDを謳う会社も多いです。
多くのスキルが求められる
同じ作業を繰り返すだけの単純作業者、定型業務従事者でなければ、ビジネスに必要なスキルがまんべんなく求められます。
専門分野に加えて、PC(パソコン)、ビジネスライティング(文章)、のほかたくさんのスキル領域があり、高い給料を得ようと思うと、より高いレベルでのスキル習得が必要になります。
保育士経験があると、対人コミュニケーションスキルの高い人は多いかもしれません。そこは生かせるでしょう。
保育士・幼稚園教諭から一般企業への転職で、保育士経験を効果的にアピールする8つの方法
給料は一般企業のほうが高い
多くの保育士さんとお話しすると、給料が安い、ということが大きな不満であることが多いです。
保育業界では、経営者や役職者は別ですが、保育業務メインで働いていると、400万円台が限界ではないでしょうか。200万~300万円台の人がほとんどだと思います。
会社では、業種にもよりますが、社員数が数百人規模を超える会社であれば、給料は安定して伸びます。一口に一般化は難しいのですが!安く見ても、だいたいの目安で、
20代
給与 25万円×12カ月
賞与 50万円×夏冬
これで年収400万円となります。これだけみると、保育士の給与と大きく変わりません。
平社員でもグレードが分かれている、という会社が多いので、昇進試験に合格して昇格すると、給料が急増します。多少がんばってひとつふたつ昇格しておけば、
30代
給与 30万円×12カ月
賞与 70万円×夏冬
年収500万円に達します。その後も給料は微増します。これで、保育士を続けていた場合と比較すると、生涯賃金は数千万円の差が付きます。
会社によっては、平社員でも活躍して実績を挙げれば、年収1000万円を得ることも十分に可能です。
「会社員経験なし」から一般企業を目指すには
会社員としての業務経験がない中で、会社勤務を希望する場合、どのように職を探せばよいのでしょうか。いくつか手段はありますが、どのような職種を希望するかによってその方法は異なります。
「この会社のこの職種が希望」ということなら、その会社のホームページで中途採用募集を検索したり、なければ直接電話して期間従業員採用はあるか問い合わせたりします。「希望する職種は決まっているが地域は限定的」なら転職支援サービスを利用します。本記事内でも、転職支援サービスをいくつかご紹介します。
いずれにしても、「特に職種の希望はないが、なんとなく会社勤務がいい」という気持ちでは、採用を勝ち取るのは難しいです。世の中にどのような仕事があるか調査の上、希望職種を定めてから動きだしましょう。
![]()
転職支援サービス
たくさんの転職支援サービスがあります。サービス会社によってやり方は多少異なりますが、履歴書や職務経歴書は必要になるでしょう。
自分の希望する、
・職種 (例 経理、一般事務など)
・業種 (例 メーカー、商社など)
・勤務地 (例 都内、1時間以内など)
・勤務体系(例 正社員、派遣など)
を、だいたいまとめておくとよいでしょう。
自分の希望がまとまらない場合には、転職支援サービスに何社か登録し、さまざまなお仕事案件を検索して、自分に合う職種を絞りこんでいきましょう。
サービスに登録するだけでしたら、どこも無料です。
会社のホームページ
会社の希望がピンポイントであれば、その会社のホームページの「採用情報」の中の「中途採用」「キャリア採用」などの項目から、求人を探します。
希望の職種があれば、直接応募することも可能ですが、その求人を扱う就職支援サービスに相談すると、確実に進めてくれるのでおすすめです。さまざまなアドバイスももらえます。
電話、メールで直接問い合わせる
古くさい手法ですが、希望の会社の担当者と直接情報交換できます。
期間従業員の募集情報や選考のプロセスを教えてくれたり、就職支援サービス会社を通す旨を教えてくれたりします。
一般企業の勤務経験なしで会社に中途入社するには
中途で入社する社員には、多くのスキルが求められます。時間とお金をかけて教育しなくても、即戦力として活躍してもらえるところに中途採用の価値があるためです。
専門性やそのほかのビジネスマンとしてのスキルを漏れなく要求されることはありません。しかし、ひとつでも多くを習得しておくこと、どんなスキルが必要かを知っておくことで、ほかの候補者と差を付け、採用内定を勝ち取ることができます。
必要なスキルについてまとめた記事を、ご参照ください。
一般企業の経験なしで、会社の中途採用に合格する 知っておくべき10のスキルを解説
一度転職しても、保育士への復帰は大丈夫、むしろメリットは多い
保育園では、基本的に保育業界での経験者がほとんどです。したがって、以下のようなことができるスタッフが園に多くいるということはありません。
・プロのビジネス目線で日常業務を改善
・保育サービスの革新
・掲示物や配布物(紙)のプロ並みのデザイン
・敏感なコスト感覚
保育士は、子供の健康と安全を守ることが最優先ですから、もちろん、それを第一に考えていただいていいと思います。ほとんどの人がそうであるべきでしょう。
しかし、園長先生は経営者であることが多いため、保育だけでなく、全体の運営に関わってビジネス視点で考えなくてはなりません。経営・ビジネスコンサルタントと契約して、アドバイスをもらえる環境にあったとしても、毎日の保育業に付きっきりで進めてもらうわけにはいきません。
そこで、保育業の経験、会社でのビジネススキルの両方を兼ね揃えた人であれば、運営の右腕になってもらったり、副園長や主任候補として重宝してもらえることになるでしょう。(中にはワンマンな園長もいますが、園の方針によります。)
会社員として働くと、多くのビジネススキルが身に付き、保育士に復帰したいと思ったときには、パワーアップした状態での復帰が実現することになります。
まとめ
保育園と会社の違い、アプローチの手法などの情報をお届けしました。保育士経験だけだと会社への転職には自信がなく不安もあるとは思いますが、まずは、転職支援サービスを利用し、プロの意見も参考にしながら進めてみてください。
必要なスキルについては、本サイトのほかの記事も参考になると思いますので、ぜひご覧ください。