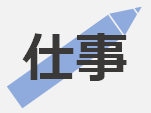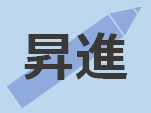就職活動でも転職活動でも、自分が就職する会社は慎重に選びたいところです。自分の就職した会社によって自分の人生が左右される、と言っても過言ではありません。
この記事では、筆者が大手企業と中小企業、さらに小規模な会社で勤務した経験から、さまざまな比較をして、どちらが良いか悩んでいる人にとって役立つ情報をお伝えします。
大手企業と中小企業のおおまかな違い
大手企業と中小企業のどちらも一長一短あり、自分の性格や働き方によりますので、どちらが良いということは一概には言えません。
中小企業とか大企業とは、資本金や従業員数などで正式な定義はあるのですが、だいたい一般的には、数十人から数百人程度の従業員数の会社を中小企業と呼ぶことが多いです。
従業員が50人の会社から見たら、従業員1000人の会社はたしかに大企業かも知れません。
しかし、大企業、大手企業は数千人とか数万人の従業員数であり、この規模から見ると、従業員1000人の会社も中小企業として位置付けられることがあります。
大手、中小という正式な括りで見ることが重要ではなく、大きな会社と小さな会社の違い、というくらいの感じで捉えてください。
中小企業のメリット
中小企業に勤務して感じたメリットはたくさんありますが、主に以下のような内容です。
1. 部署の数が限られているため、社内での業務遂行が速い
2. 社内での仲間意識が生まれ易い
3. 敷地、社屋が大きくないので、社内での移動が楽
4. 本当に必要な業務だけに取り組めてスキルアップ出来る
5. 昇進が早い、し易い
これらの逆が大企業のデメリットになる訳ですので双方を比べながら説明します。
1. 部署の数が限られているため、社内での業務遂行が速い
社員数が少ない、ということは、社内で構成される部門数もたくさんありません。自分があるプロジェクト業務を進める上で、勝手に自分の思うままに進めるということは出来ませんから、いわゆる「関連部門」という人達に伝えたり合意をもらいながら進めなくてはなりません。
例を挙げますと、
自分は商品開発部門で働いていたとします。新しく開発した商品を具体化するにあたり、情報共有し、了承を得ながら進める部門は、
中小企業:営業部、生産部、品質管理部、以上
大企業: 事業企画部、販売部、販売促進部、デザイン部、生産管理部、製造部、
製品品質評価部、量産推進部、商品プロジェクト推進部、生産技術部、
梱包技術部、有限要素解析部、製造品質部、部品管理部、
試作製作推進部、物流部、開発管理部、市場品質支援部、法務管理部、
環境保証部、資材調達部、購買部、など多数で、子会社や関連会社もあり。
大企業の場合、このように社内の膨大な数の部門や関連子会社と業務調整しながらでないと、物事が先に進みません。
自分がメカ機構開発課のスタッフであれば、電気技術課や光学系開発課、ソフト開発課など、同じ開発部の中の他課と足並みを揃えないといけません。
もちろん自部門の人間、上司や同僚の理解も得ながら進めることは大前提です。
大企業では、このような環境の中で仕事を進めていく上で以下のようなスキルが求められます。
交渉術
スケジュール管理力
専門知識
情報伝達力
プレゼン力
業務調整力
資料作成スキル
人間力
全体を見通す感度
物事の優先順位付け
体力と精神力
場合によっては語学力
などです。
総合的なスキルがないとダメです。どれかが欠けても業務遂行中につまずきます。
中小企業ではこれらのスキルが無くても良い、という訳ではありませんが、常に他部門との調整業務やら説明のための資料作成、その都度のスケジュール管理などで身も心も疲弊するということは少ないです。
中小企業での忙しさの原因は、業務範囲は広くないが仕事そのものが多いのになかなか人員の補強がされない、ということが多いです。しかし業務を進める上での面倒くささは有りません。なかなか物事が先に進まない、この部署のコイツさえ居なければ、というストレスはほとんどありません。
2. 社内での仲間意識が生まれ易い
人数が少ない、ということは組織の規模も小さく、業務で関わる人数にも限りがあります。仕事を進める上でいつも同じ人達が現れます。
もちろん性格的に相性が良いか否かが先ですが、いつも一緒に仕事をすると自然に仲良くなれることが多いです。仮に業務遂行がうまく行かなくても、お互いにフォローしながら穴埋めできます。社員数が少ないことで、社内ですれ違う、仕事で関わる、文化活動で知り合う、など大体顔ぶれも分かってきて、話が通じ易くなります。
数人で飲みに行ったときに、同席するといったことも頻繁に出てきます。
大企業では、社内に必ず敵が出現します。これは大企業ならどこに行っても必ずいます。1年間で社内で何十人何百人と関わり、皆が自分と気が合うということは、まずありません。自分の進め方や自分の部門を激しく中傷するような過激な人もいます。
大企業ではアットホームなゆるーい雰囲気で仕事を進めることは稀で、なめられないようしっかり予防線を張っていることがあります。性格的に温厚な人が居ても、自部門の看板を背負って出て来ている以上、スキを見せない人がほとんどです。
自分が業務を進める時に、関連部門で性格的にややきつめの人で、自部門のスタイルをくずしたがらない人がいた場合、その人はおそらくあなたの敵になるでしょう。
新しい取り組み、とか自部門発意で何かを進める際には特に厄介な存在となります。
大企業では、自分が仕事上で失敗をやらかすとその影響の範囲が広く、自部門だけでなく多くの関連部門に及ぶため、ほとんどの社員がかなり慎重に物事を進めます。
中小企業では、いわゆるアットホームな空気を感じ、同じ会社の人達は仲間、といった感覚を持っていました。筋の通った説明をして業務を依頼するための資料作り、などは不要で、同僚や先輩を頼ったりして、「頼むよ~」みたいな慣れ合いで仕事が進んでしまうようなことも多く見られました。
3. 敷地、社屋が大きくないので、社内での移動が楽
中小企業の勤務地で敷地がメチャクチャ広い、ということはほとんどありません。
従業員数が少ないわけですから、事業規模も小さいため広い敷地も必要ではないのです。敷地が広ければ当然税金も多く掛かるため、広い敷地を構える意味がありません。
長い会社員人生の中で、敷地内を移動する時間が多いと、その時間は単に無駄な時間となります。大企業でも支店や小規模事業所であれば狭い敷地内で仕事できますが、もし地方の生産工場などに配属された場合は地獄です。敷地の端のほうの自分の建物から他の実験棟等まで歩くと10分とか20分とか掛かるケースが本当にありました。
例えば試作品を運んで移動するという場合、雨が降ったら計画を急きょ延期して晴れている日に運ぶ、ということもあります。廃棄物を捨てに行くにも建物間の移動が発生したり、他部門の事務所に打ち合わせに行くにも何分か掛けて移動します。エレベーターで一階に降りて、移動してまたエレベーターを待って上がって、、、。
外回りの営業マンは移動時間も仕事のうちですが、出張もしないのに勤務事業所で一日に20分も30分も移動のために掛かるというのが現実です。年間でどのくらいの時間が移動のために費やされているかというと、
30分/日 × 250日/年 = 125時間
一日7.5時間勤務とすると、実に年間で16日分は移動で歩いている、という計算になります。こんな時間があったら、何かの自己啓発に使いたいところです。
中小企業で働いていたときは、勤務時間をとにかく「仕事」に費やすことが出来ていました。これは、自分の成長や知識・経験の積み上げのために貴重な時間を送ることが出来ていて本当に良かったと思います。
必ずしも大企業は広くて中小企業は狭い、というわけではないですが、
大企業 ⇒ 狭い敷地もあるが、製造業で生産工場配属だと大抵は大規模な敷地
中小企業 ⇒ 高い確率で狭い事業所
という具合に考えておくと良いです。
敷地の遠い所に保管していた書類やサンプル品が急に必要になった時など、まさに地獄です。
余計な移動に膨大な時間を割かないで「仕事」の部分に時間を費やせることは、大きなメリットと言えます。
4. 本当に必要な業務だけに取り組めてスキルアップ出来る
スペシャリストとしての自己成長を重要と考えている方にとっては、かなり重要な要素です。
中小企業は、大企業と比較すると財政的な体力は劣ります。事業で失敗しては会社の存続に関わる事態となってしまいますから慎重に手堅く事業に取り組みます。会社の売り上げ・利益になるような仕事に重点的に取り組むことになります。
また会社の規模が小さいことで、取り組むプロジェクトがあまり大きくないことが多いです。数ヶ月や数週間といった短期間での納期が設定されることが多く、その締め切りに向けて必死に取り組みます。そのため、余計な必要不可欠でないプレゼン資料やお作法の部分はあまりうるさく言われない傾向が強いです。
会社とは、本当は利益になるためのお仕事だけでなく、たくさんの従業員が快適に安全に仕事が出来るような体制づくりや地域に対しての社会的責任を果たせるような取り組みをしなくてはなりません。大企業はとにかく、対外的にも社員のためにも「ちゃんとしていないといけない」ため、以下のようなことに膨大な時間を割きます。
整理整頓活動や巡回などに膨大な時間を割く
企業の社会的責任(CSR)などに関する講習実施
下請け法の周知徹底へ時間を割く
安全教育や未然防止活動の過剰なまでの実施
物品や書類の詳細な管理
大人数に情報共有するための長時間の会議
新人教育、研修期間に何年もかける
徹底出来て当たり前、と思える事もありますが、新しいプロジェクトや商品・サービス開発をいくつもこなしながら、これらの事を業務時間に突っ込まれては、本業の仕事のほうがなかなか進みません。もちろん中小企業でもこれらに取り組むことあるのですが、全社を挙げてこのような業務外の取り組みに徹底的に時間を割けるような中小企業はとても少ないのが現状です。本当はやりたいけど、時間や人員などの都合で出来ないのです。
信じられないかも知れませんが、大企業で営業担当として働くあなたの一日の業務が
「整理整頓活動」
「安全衛生を向上させる業務」
「自分に深くは関係ない長時間の打ち合わせ」
だけで終わることもあります。
あなたが大企業に入社したら、「何でこんな事に時間をたくさん使わなきゃいけないんだろー」と思いイライラする時が頻繁に訪れることでしょう。
中小企業では自分の業務に直接関係のある、いわゆる「実務」の部分に割ける時間が圧倒的に多いのです。
自分が担当する専門分野での業務に掛ける時間が、中小企業のほうが大企業より多い、ということであり、すなわち専門スキルを上達させるには、中小企業のほうが密でしかも早い、ということになります。もちろん会社のレベルや個人の吸収スキルにも依りますが、一日中その専門分野の事を考えていられるのと、あれこれどーでもいいことに気を配らなくてはならないのを比較すると、専門スキルの構築には明白な差が出てきます。
中小企業で専門分野に特化した取り組みを出来るメリットの「未来への強大な破壊力」についてお話しします。
大学卒業後の入社3年後くらいを想定します。
大企業では場合によってはまだ新人教育期間中である可能性があります。または配属まだ間もない時期でしょうか、、?
しかし中小企業では、そんなに悠長に新人研修に時間を掛けられないので数ヶ月の研修期間を経てさっさと部門に配属し、バンバン実務をこなして行きます。
もしあなたが20代半ばから後半で転職をしたい、と思ったときに、大企業と中小企業では専門スキルの吸収具合は中小企業で働いていたほうが遥かに大きいです。
既に3年4年とその専門分野で仕事をしていると多くの事を吸収しているのが自分でも実感でき、自身も付いています。それに比べて大企業ではその3年間は、なんか色んな事をしてきたがまだ自分が何を出来る人だか明確ではない、といった状況です。その大企業の社員である♪ということだけではないでしょうか?
専門スキルを持って自分を新しいフィールドに導けるのは、その実務に密着した豊富な経験と知識です。
自分を迎え入れてくれる先の会社の人達は、あなたに対して
片付け出来る人か?
安全に気を配れる人か?
打ち合わせにちゃんと出てくれる人か?
管理を徹底してくれる人か?
コンプライアンス意識の高い人か?
ということに対する期待は大きくない傾向にあります。そんなことは入社してから徹底してもらえばいいのです。専門スキルをもっていて、自分たちが考えつかない視点でのさまざまな実績や問題解決などを経験してきている人材を求めています。
専門スキルを短い時間で上達させる上で、中小企業に入るメリットは大いにあります。
5. 昇進が早い、しやすい
中小企業では、昇格、昇進が早いです。
もちろん社員数が少ないので、競争もそれほど激しくないし、がんばって仕事をすれば課長くらいまでは、たいてい昇進できます。
大企業では、ひとつの課の課長のポジションで仕事をする上での自部門スタッフ、他部門に対して与える影響の範囲が大きいため、課長のポジションに就かせる上での判断基準が非常に高いのです。この人を一つの組織のトップに就かせて本当に問題ないか、慎重に決協議されます。多くの候補の中から厳選された社員にそのポジションを与えます。競争は熾烈です。
大企業に見る課長以上は、人前で罵倒したり感情的にキレたり、支離滅裂なことを言ったりする人は非常に稀です。
それに対して中小企業では、そのハードルは高くはなく、売り上げ実績を挙げたり、上司の言うことをよく聞く、気に入られる事で課長になれたりすることがあります。たとえ適任でなくても、その影響の範囲は狭く、大事にはなり難いです。
中小企業では、ほかに切実な事情もあります。どの会社も、課長は「会社側の人間」となります。主任、係長クラスまでは労働組合の組合員であり、残業代が発生します。課長になれば会社側の人間であるため年俸制となり、残業代が出なくなります。主任、係長は残業代で稼ぐとも言われ、課長の給料を超えるということもよく聞かれます。そのため、残業代のかかる係長クラスは、さっさと課長にして人件費を抑える。会社にとっては都合が良いのでしょう。
課長ではなく、「担当課長」という素晴らしいポジションがあり、部下の面倒を見たり人事労務管理をするのではなく、業務やプロジェクト、専門技術、課内の小さな取り組みを束ねるような立ち位置です。
担当課長がウヨウヨ居る、という会社もあります。なんでこんな人が課長なの??と思うこともよくありました。
中小企業に勤務して、毎年のノルマをしっかりクリアし、よく上司の言う事聞いて、しっかり仕事の管理をして、後輩の面倒をみて、人当たり良く対応していれば、かなりの確率で課長クラス以上にはなれます。大企業では、そんな人はいくらでも居てその中で勝ち抜いていかなくてなならず、しっかりやっていても定年まで平社員、ということはよくある話です。
給料はともかく、課長、部長などのポジションに憧れるなら、大企業より中小企業です。
続いて大企業のメリットを解説します。
⇒大企業に就職するメリット