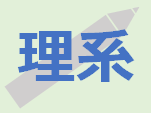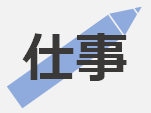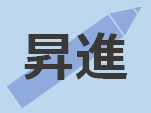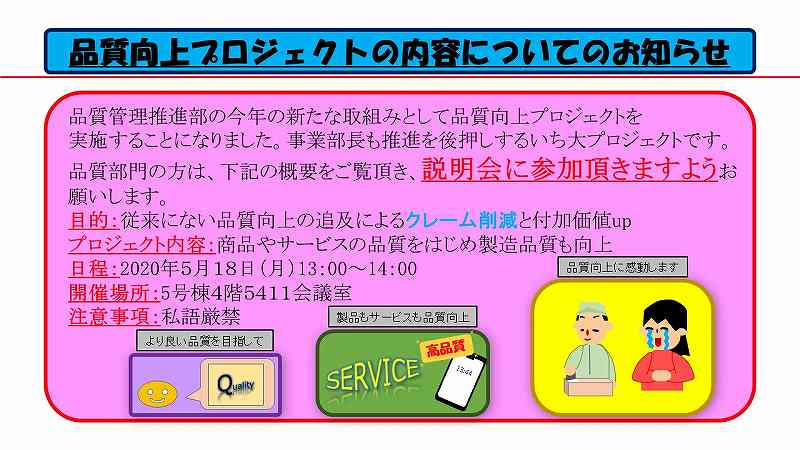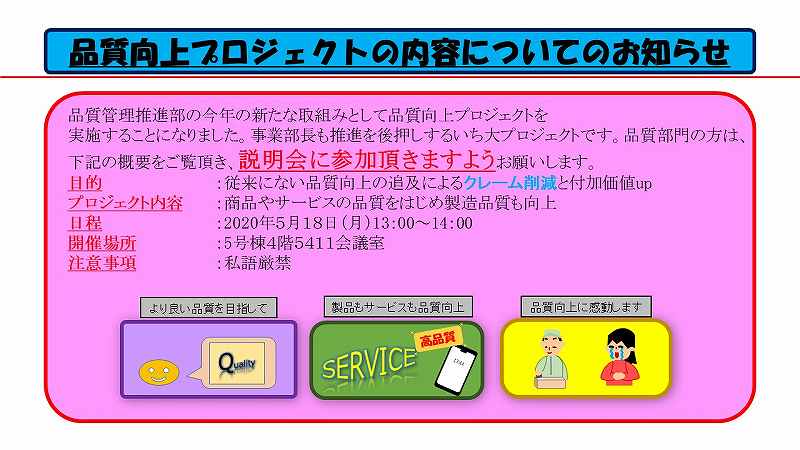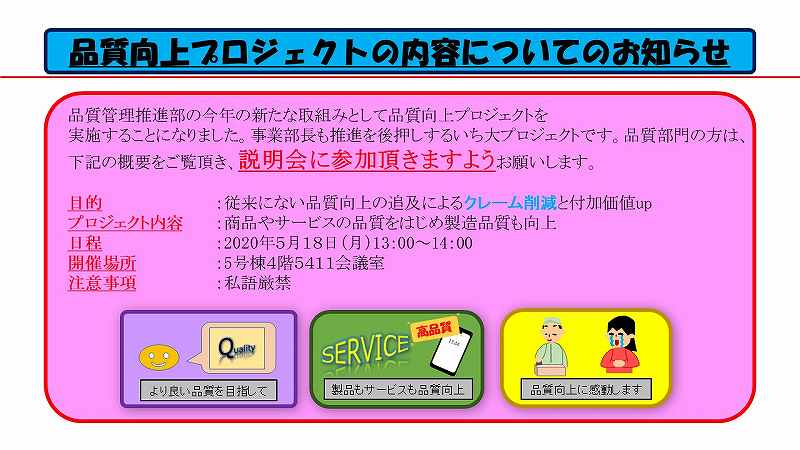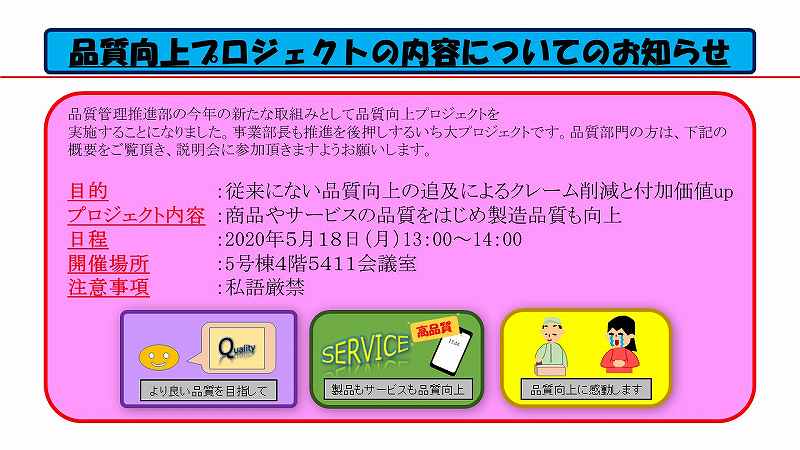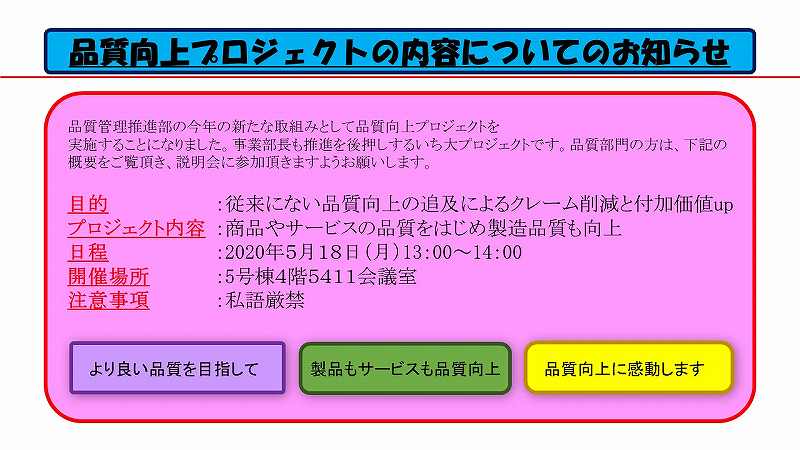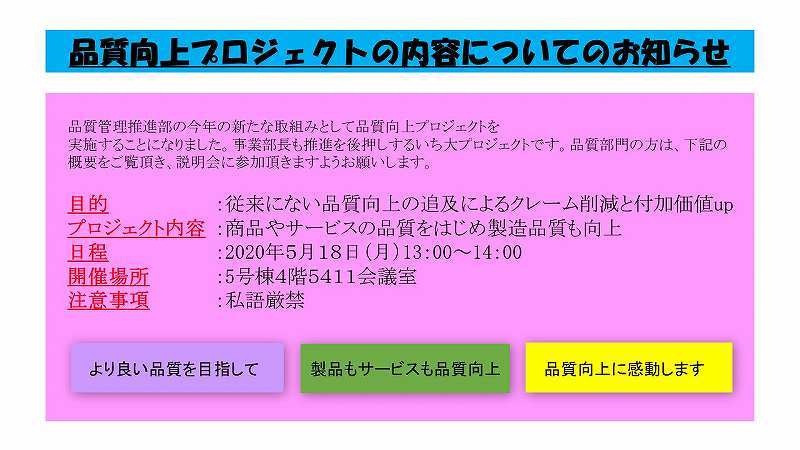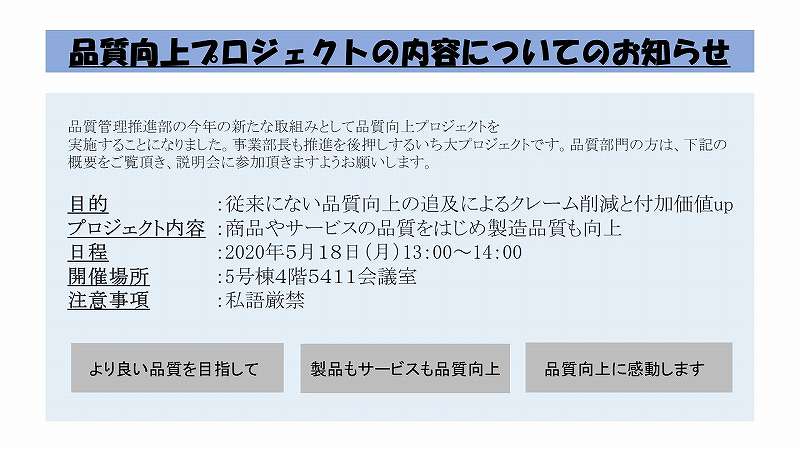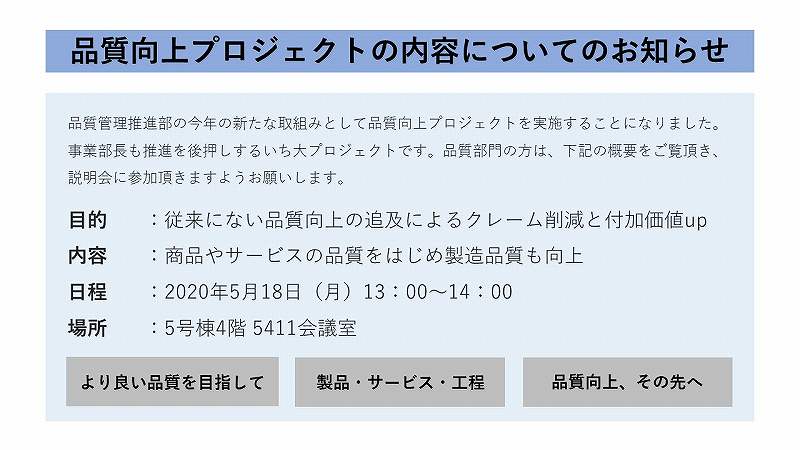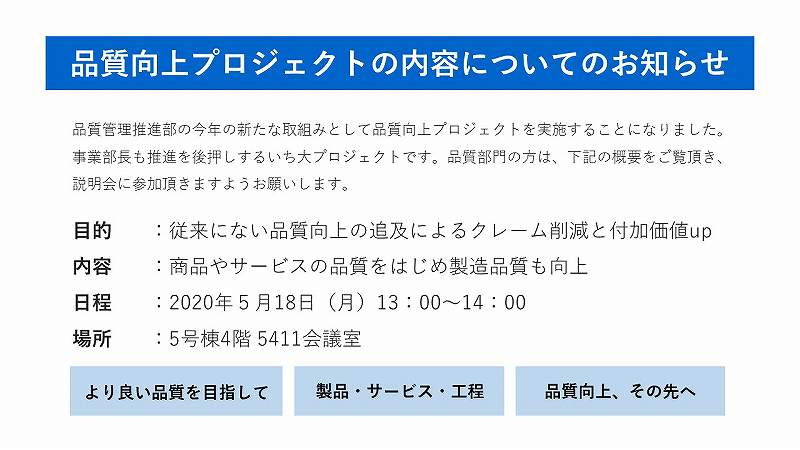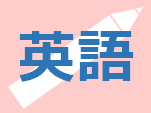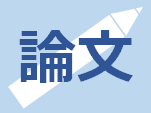成果主義、実力主義が一般化してきた現代社会では、学歴が問われることは少なくなりました。しかし、大学で体系的に広く学問を学んでいないと苦しくなる職種があります。技術職です。
医師、弁護士、薬剤師など、大学での学問と国家資格ありきですが、電気、機械、化学といった技術職は、その職に就くための資格は必要ありません。会社によっては希望によりその技術職に就けてしまう場合があります。
この記事では、技術職に就くために大学で学ぶ必要があることについて解説し、さまざまな具体的事例をご紹介します。
理系の大学で学ぶことは? おさらい
学部や大学によって異なる部分もありますが、理系の学部では以下のようなことを学びます。
- 専門分野
- 専門基礎分野
- 専門の実験・演習
- 語学
- 一般教養やスポーツ
たいてい専門分野の科目ボリュームが最も大きく、難易度も高いです。
専門基礎分野というのは、幾何学や微分積分、力学などで、専門教育の基礎となる学問です。
専門分野における実験や演習も多く課せられていることで、座学だけでなく実際のモノの仕組みや現象、理論を体感できる機会を経験します。
語学については英語が必須で、第二外国語として中国語やフランス語、ドイツ語などが課せられる場合もあります。これらに加え選択科目としてイタリア語、ロシア語、韓国語などさまざまな言語を学ぶことも可能です。
一般教養は幅が広く、文学、教育学、考古学、経済学、数学などほとんどの人文科学・社会科学・自然科学の科目を学ぶことができます。スポーツの授業やスポーツ科学も選択できる大学が多いです。
このように大学では、専門科目を中心とした多くの学問を修めます。ひとくちに「電気科で学びました」と言っても、体系的に電気について学び、関連する学問や語学をはじめとするそれ以外の教養を広く学んだことを意味します。
技術職のためになぜ大学で学ぶ必要があるか
仕事で技術的な業務を1つ遂行する場合、その行為そのものの知識だけでなく、本人も気付かないくらいに多くの周辺知識が生かされています。
たとえば機械設計を例に挙げます。「ある装置にモーター機構を追加する」という設計行為にあたっているとき、どのような知識が用いられているでしょうか。
「要求する駆動スペックと寸法を確認して専用のカタログからふさわしいものを選び、CADデータをダウンロードして図面や3Dモデルに落としこむ」
一見、問題なさそうですが、これはただの設計オペレーションです。
今回の設計行為の場合、以下のような知識やスキル、観点も求められます。
- 設置場所は屋内/屋外のどちらか? 屋外であればモーター部品の耐候性や防水性は問題ないかを見極める
- 本装置以外からの振動が加わる環境なら、接触部の磨耗は問題ないか? 問題ありそうならゴム材をかます
- 取り付けにはスプリングワッシャーは必要か? その判断基準は?
- 重力加速度Gがかかる場面はないか? あるならどんな策を講じるか
- プラスチック材料は介在しているか? その場合に何に気を付ければいいか?
- 全体の剛性感は問題ないか?
- 取り付けはタッピングか、溶接ナットか、ナットか、ボルトか、ネジか、ザグリか、などさまざまな選択肢
- モーター機構以外に本当にほかの選択肢はないか?
- 手動の機構もあるがそれではダメか?
上記の発想が自然に頭に浮かぶには、材料力学、金属材料、非金属材料、振動工学、工業力学などの機械工学の専門分野の体系的な幅広い知識のほか、本質や根本的理由を問いかけるwhy型思考、漏れなく事象を網羅するフレームワーク思考などが基盤となっています。大学で体系的に学ぶことで、さまざまな側面から設計行為をとらえることができるわけです。
機械工学でいえば、それ以外にも流体力学やロボット工学、機構学、メカトロニクス、熱力学、コンピューターグラフィック、計算機解析、自動制御など、ここには書ききれないくらいのさまざま分野を学び、設計対象の変化に応じて用いる知識を総動員します。
大学での学問を修めていれば、1つの単元を半年や1年一生懸命学ぶことで少なからず頭に残り、どんなことを学んだかは覚えています。そういう分野があったから、このように調べれば答がわかる、という引き出しが頭の中にできます。たとえ時間が経過しても、引っ張り出すことが可能です。
大学で学んでいないと「この専門領域にはこのような学問がある」ということを知りません。「自分がそれを知らない」ということすら知らないわけです。
先ほど、why型思考とかフレームワーク思考などと書きました。そのような思考力を学問として大学で教わることは稀でしょう。しかし大学では4年間でさまざまな先生から講義を受けますので、その中では「本質をとらえよ」「現状を疑え」「会社ではこういう仕事の仕方を求められるから、入社前に○○に備えよ」など多くの指南をしてもらえます。考える力やさまざまな予備知識を養えます。
専門分野の英単語を定期試験に課す教授も多く、知らず知らずのうちに英単語の知識量も増えます。
海外に研修旅行に連れていってくれる教育熱心な教授もいます。
4年生の研究室ではその道の専門家から、専門知識だけでなく、その知識の実業界での生かし方、活躍の仕方、技術的な話の論法などの有意義なお話を聞けます。論文の書き方の基本も学びます。お酒を飲みながら本音で語ってくれる先生も少なくないでしょう。
元気でバイタリティーにあふれ、これから本格的な大人になる過程で学ぶ幅広い専門学問、語学、教授から直に教わる実用的知識と経験。これらは、大学で学ばずに技術職に就いた場合とは比較にはなりません。技術職として働くためには不可欠といっても過言ではありません。
大学の学問を修めずに技術職に就いた人の少し残念な事例
大学で学問を修めずに技術職として働く人を多く見てきました。もちろん優秀な方もいました。人によって異なるのは間違いありません。
しかし全体的な傾向として、残念ながら力不足と言わざるを得ない技術者は多かったです。
大学で学問を修めていないとどのような結果を招くことがあるでしょうか?いくつか事例をご紹介します。
- 概略の計算や暗算が弱い
- 三角関数や微分積分の概念が薄い
- 力学的な発想で現象を考えるのが苦しい
- 基本的な高校物理の法則での会話が難しい
- その職場での専門学問以外はほとんど知らない
これらが要因となり、問題が発生したときに1つひとつ原因の可能性をスマートに潰していくことができませんでした。また新しい発想で、従来にないものを創造することもあまり得意ではありませんでした。
問題発生時にそれを専門的な観点で漏れなくとらえることが困難な例を挙げます。たとえば製品が現地に着荷された時、製品が破損・変形していたとします。その原因をどのような側面から見るかというと、以下のようなことです。
- 形状、構造などの設計的な問題
- 組み立て不良上の問題
- 材料スペックや表面処理などの問題
- あてがう梱包材の欠品
- 梱包設計や荷作り状態の不備
- 過剰な物流条件や輸送上のアクシデント
このような大枠の視点であれば何年か経験を積めば出てくるようになるかもしれませんが、それらの詳細に関しては苦しいでしょう。
設計的な問題でしたら、衝撃値Gの想定は適切か、角度をつけた落下でのたわみのシミュレーションは問題ないか、振動でのクリープ、部材の肉厚、材料選定、曲げ部の剛性、溶接箇所、など引き出しが果てしなく必要です。
梱包設計なら、こちらも衝撃値Gの捉え方、適切な寸法マージンや安全率の取り方、自由落下時の耐久性の限界値など、掘り下げればきりがありません。
専門の部門に丸投げすると「問題ありませんでした」の回答で言いくるめられます。「○○や△△の仕様は問題なかったのですか?」と他部門にぐいぐい質問をするには、体系的な技術の引き出しがないとできません。
発生した問題が「筐体表面の異常な変色」であれば用いる知識も異なります。
大学で技術に関する体系的な学問を学ばず業務経験だけでは、パフォーマンスに限界があります。
決して無理だとはいいませんが、並大抵の努力では難しいといわざるを得ません。
大学で学ばずに技術職で成功するには
大学で技術系の学問を修めずにすでに技術系職種で働いていたり、技術系に就きたかったりした場合はどうすればいいでしょうか?
単純ですが、その分野に関して大学で学ぶことをリストアップして、ひと通り網羅することです。
関連するアクションは以下になります。
- 該当の学部や学科で学んだ人から教えてもらう
- 知人が教科書を持っていたら借りて学習
- 技術系のWebサイトやYouTubeで無料で学習
- 関連専門分野の入門編の書籍で学習
大学で経験するさまざまな実験や実習、レポートなどはどうしようもありませんので、今からの業務経験で補うしかありません。
もし時間とお金が許すなら、大学の夜間のカリキュラムで学んで大学の学位を取得するか、科目等履修生として特定の科目を学ぶ、という選択肢があります。
会社で働きながら夜間の大学に通う人を、筆者は多く見てきました。大学に行かなかったこと後悔され、夜間に通いながら本気で学んでいました。このケースですと、目的が明確な中で学ぶので、成果も大きいことでしょう。
会社では、「技術的な知識と経験」という要素だけでのやりくりではありません。社会人・会社員としての立ち居ふるまいも、成功のために心得ることが大切です。以下の記事には、そのための取り組みやコツを紹介しています。ぜひご参考にしてください。
会社で出世するために、本当に必要なことは? 実力だけではない、ちょっとした心掛け
会社の論文試験に合格する! 昇進試験、採用試験での論文の書き方のコツ、対策を解説
高専は?
大学卒でもなく高校卒でもなく、高等専門学校があります。こちらを出た方々の知識やスキルレベルは平均的にいかがでしょうか。
筆者が関わった限りでは、技術スタッフとしてのレベルは非常に高いです。16歳から5年間技術の専門科目を学びます。技術系の専門分野だけでなく、社会科学、人文科学、自然科学もまんべんなく学ぶため、大学卒の人と知識レベルにほとんど差はないのが現実です。
筆者がかつて勤務していた職場、日本の大手AV機器メーカーの開発部門でのこと、光学・機械・電気の総勢20数名の開発者の中で最も優秀な人は最若手(当時20代半ば)の高専電気科の専攻科卒でした。知識の幅広さ、発想力、問題点の発見や解決力、実行力など、高専卒エンジニアのスマートな実力を目の当たりにしました。ほとんどのスタッフが東大をはじめとする日本の上位大学卒揃いでしたが、高専の底力でしょうか。高専卒の技術に関する実力は国のお墨付きかもしれません。
大学卒の場合は、高校で3年間基本の科目を学び、大学の4年間で専門科目と社会・人文・自然科学を学びます。その7年間と高専の5年間は、技術職を遂行する上では実質的には大差はないと考えられます。
2年間の教育期間の差や、大学に入るため複数科目の計画的な勉強をする受験を突破している、といった目には見えない苦労や経験が、今日の初任給の賃金差になっているのでしょう。
ちなみに専攻科卒は、一般の大学の学部卒と同等の学歴に扱われることが多いようです。
技術職というお仕事に強く関心があれば、高等専門学校に進学することは有効であるといえます。
まとめ
技術職として働くには大学での専門の学部・学科で学問を修めたほうがいい、という理由は以下のようにまとめることができそうです。
- 大学ではその分野の技術領域を体系的に学び、また関連する基礎学問も学ぶため、知識の引き出しが整う
- 大学では専門の学問だけでなく、職務を遂行する上で助けになる一般教養も多く学び、また教授からはさまざまな個別の技術ノウハウやそれにまつわる関連教育を享受できる
- 大学の学問を修めない場合、経験と断片的な知識だけでの遂行となり、未知の領域や問題解決への対応に困難が生じる場合がある
- 高等専門学校で専門学問を修めることは、技術職を遂行する上では有効である
ただし高校卒でも優秀で出世する人が多くいることも現実です。努力によって自分の未来は変えられますので、大学卒・高校卒にかかわらず就職後してからも学び続けることは怠らないようにしましょう。
以上、技術職と大学での学問に関するコラムでした。