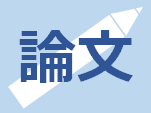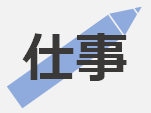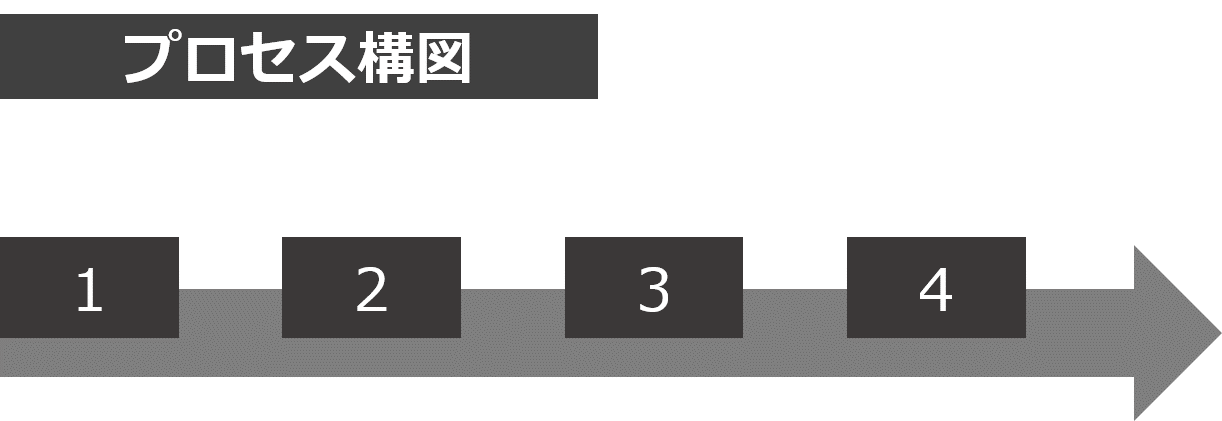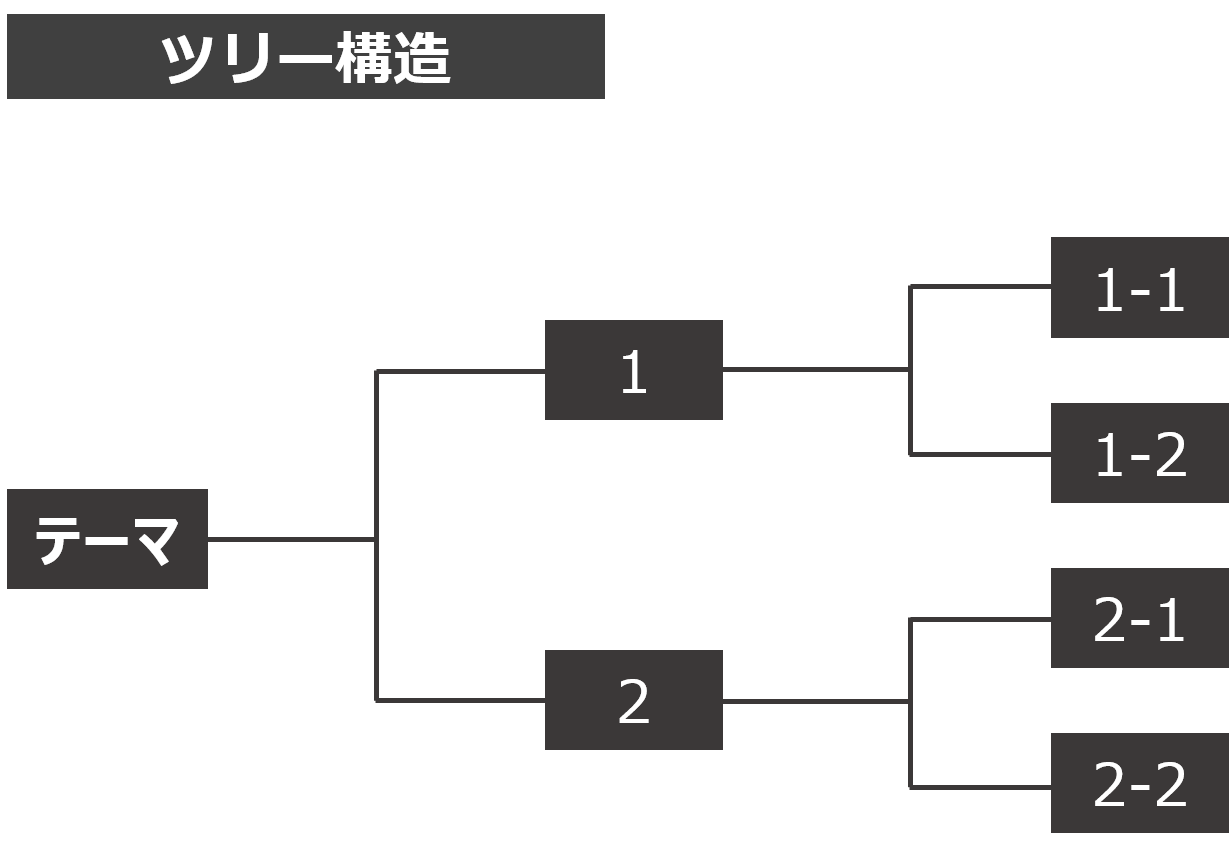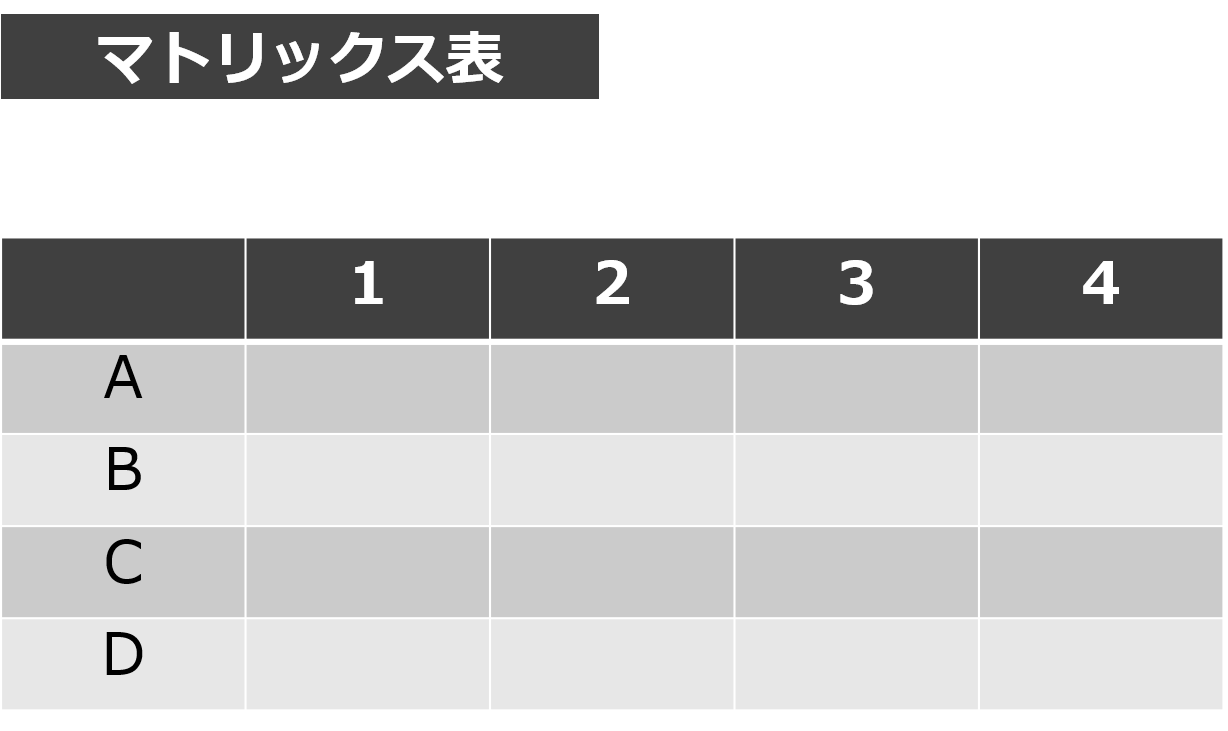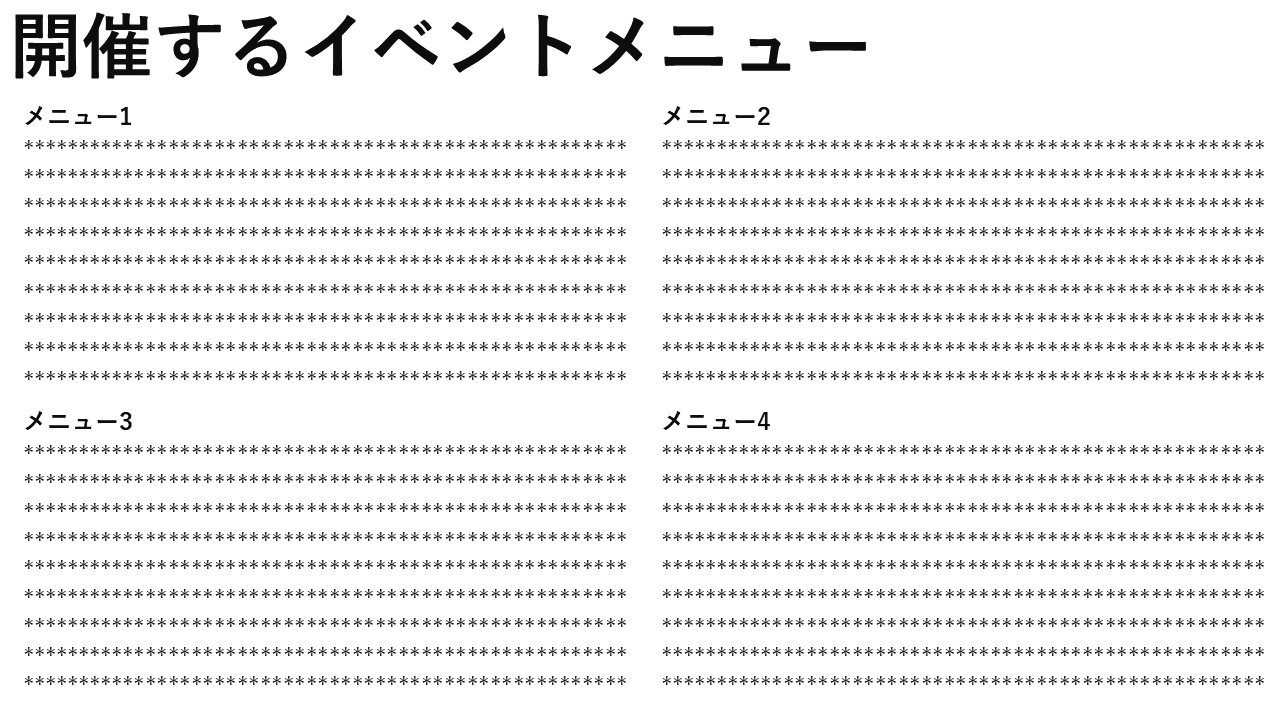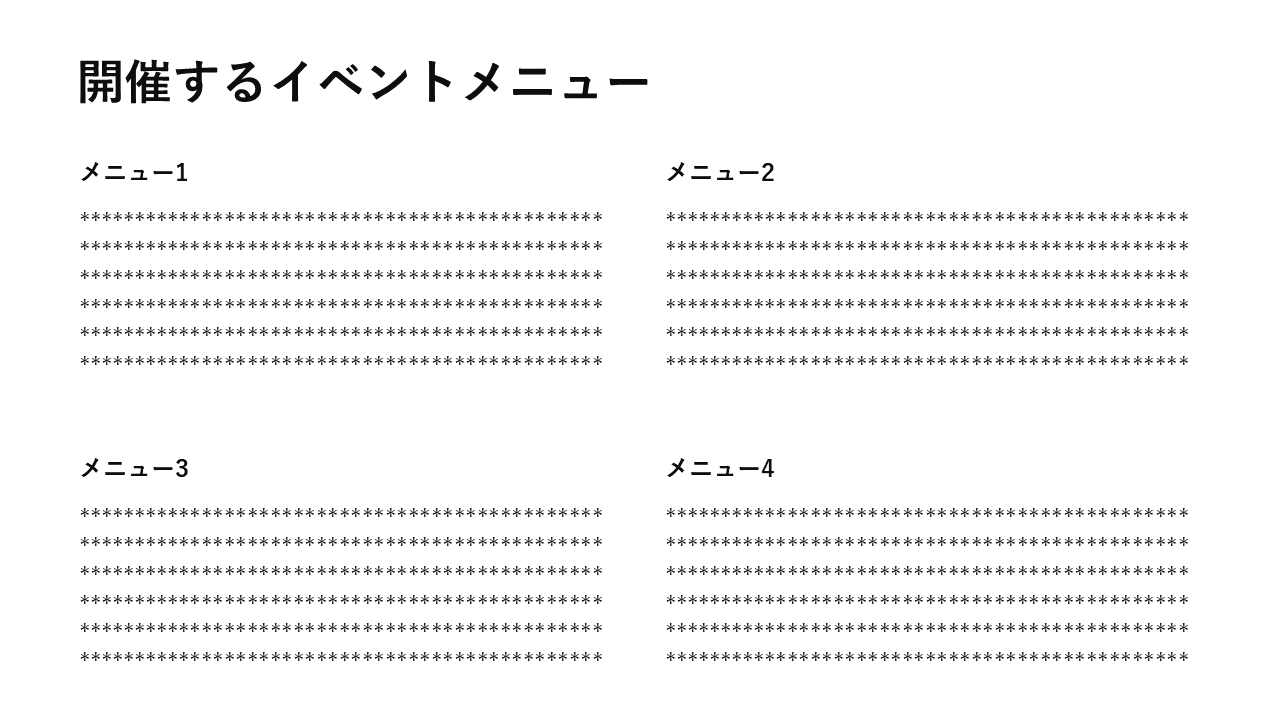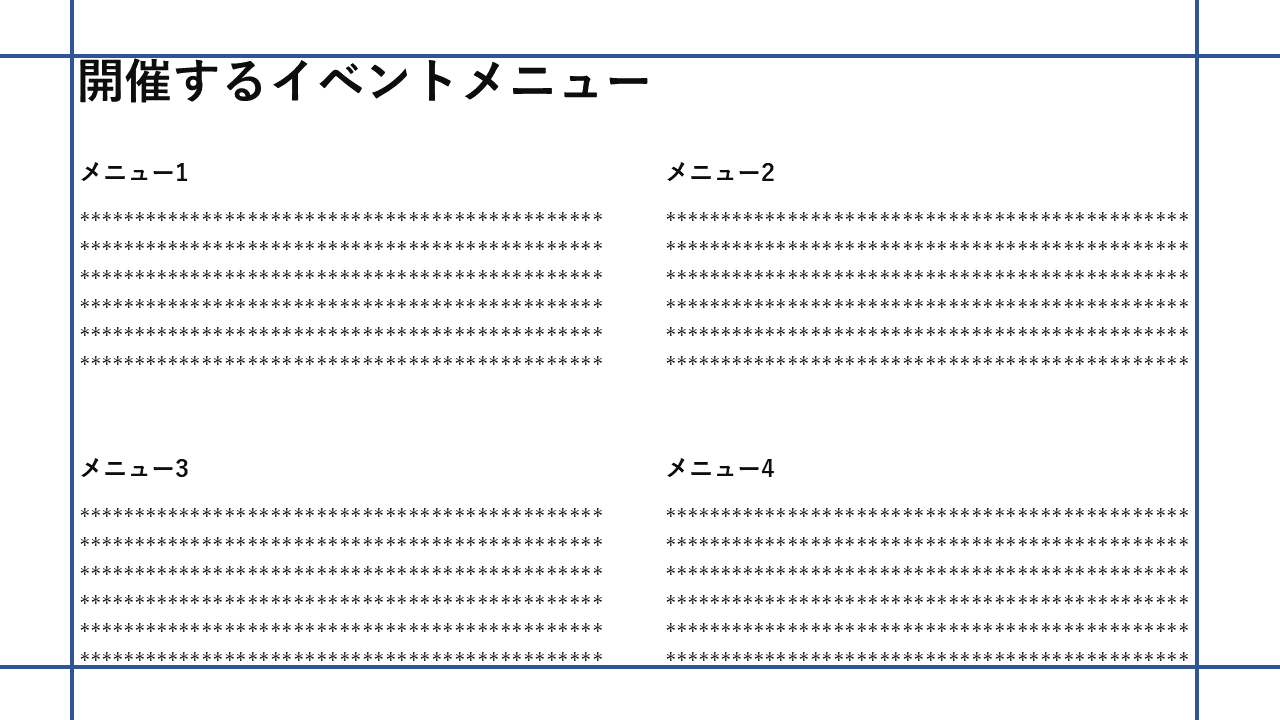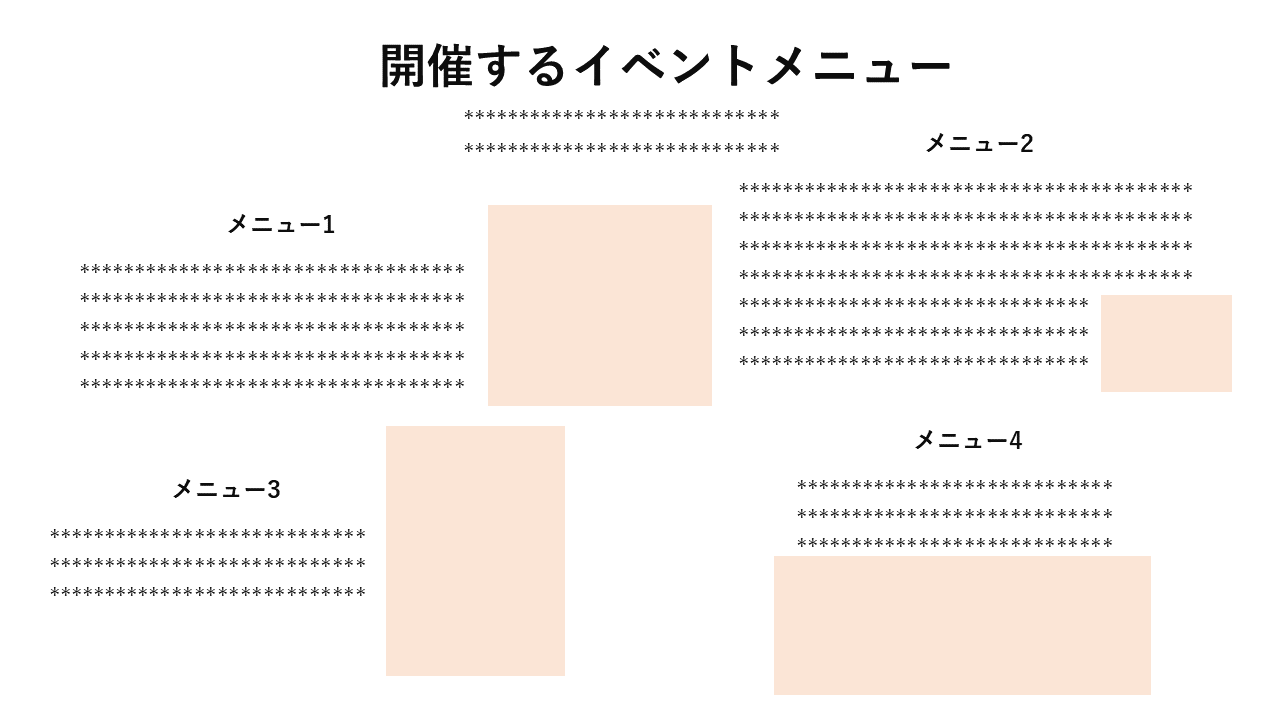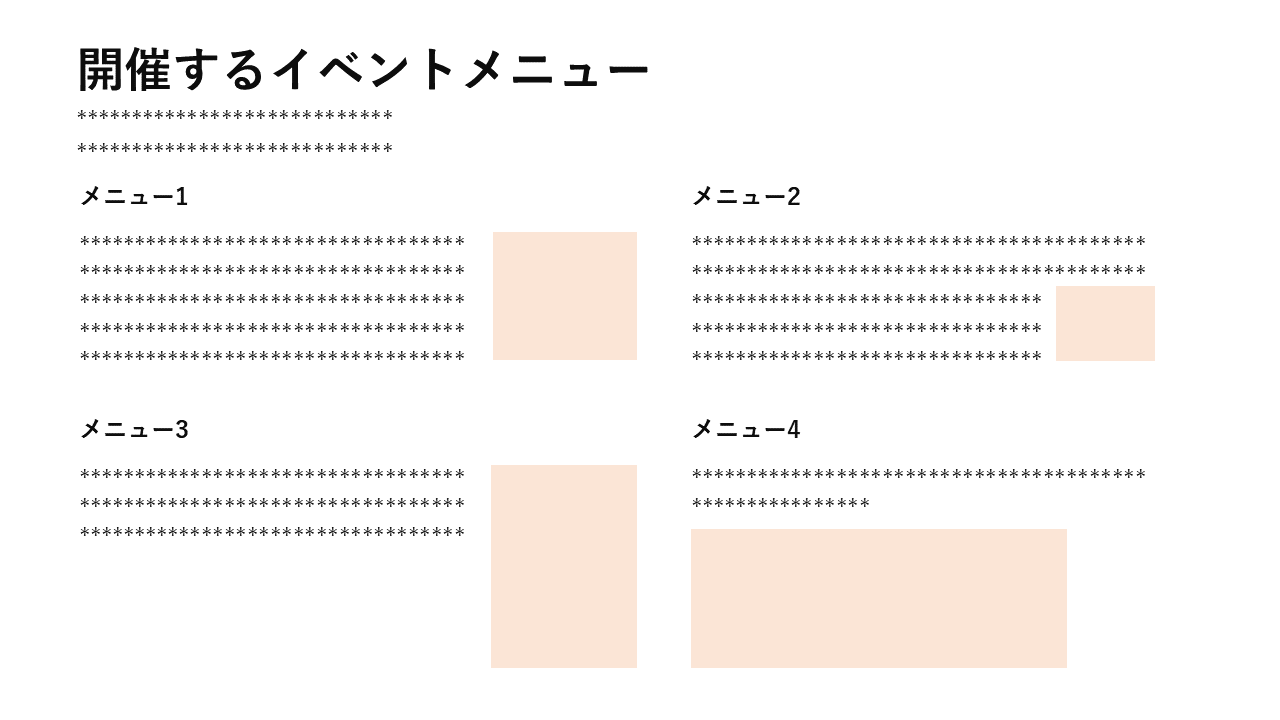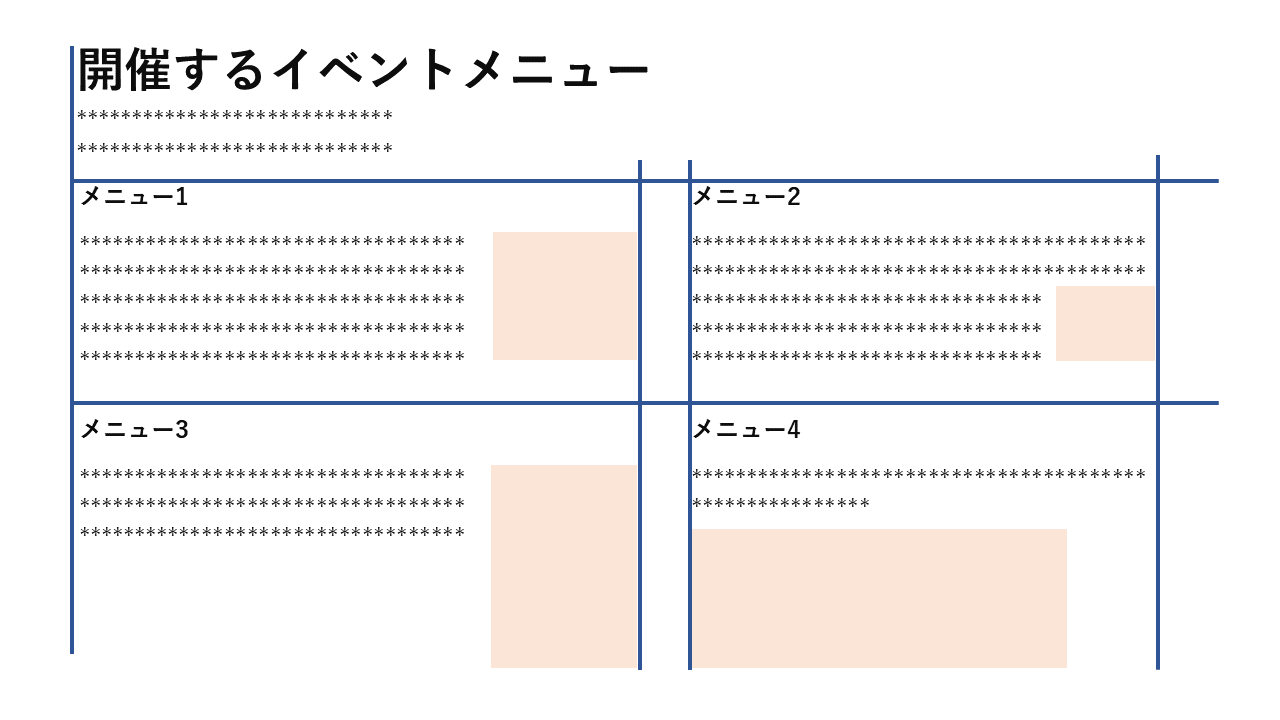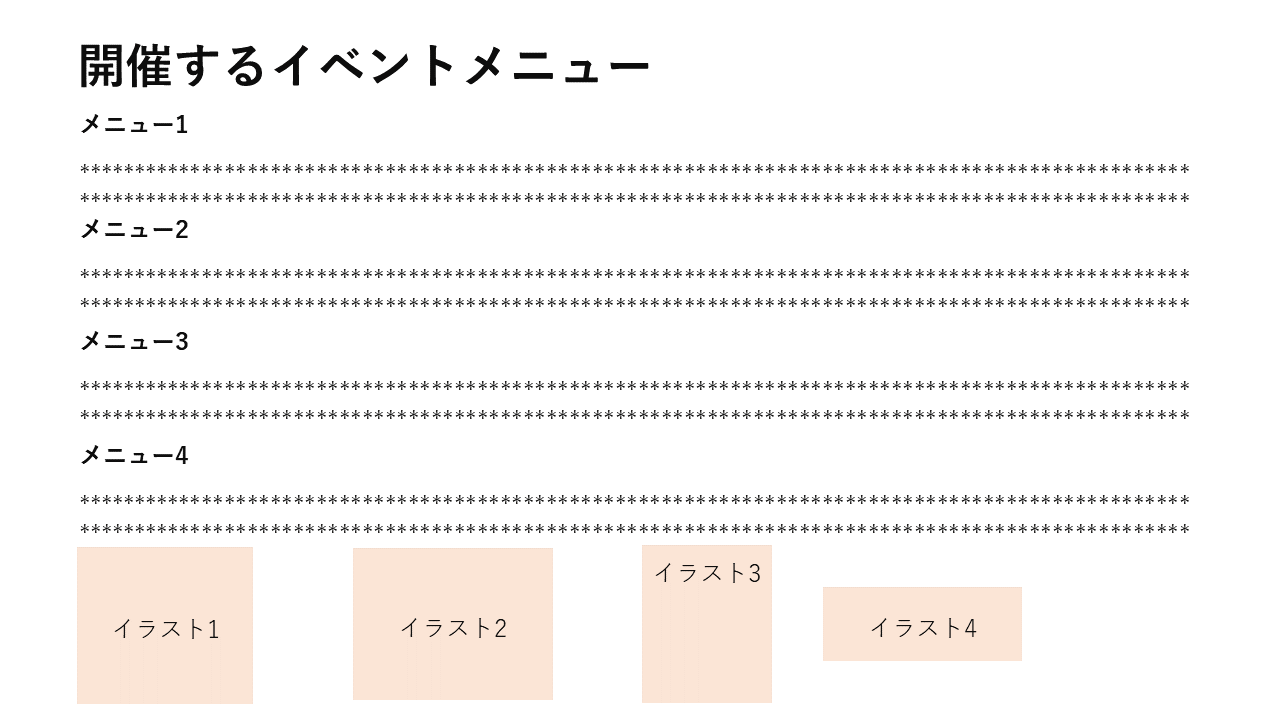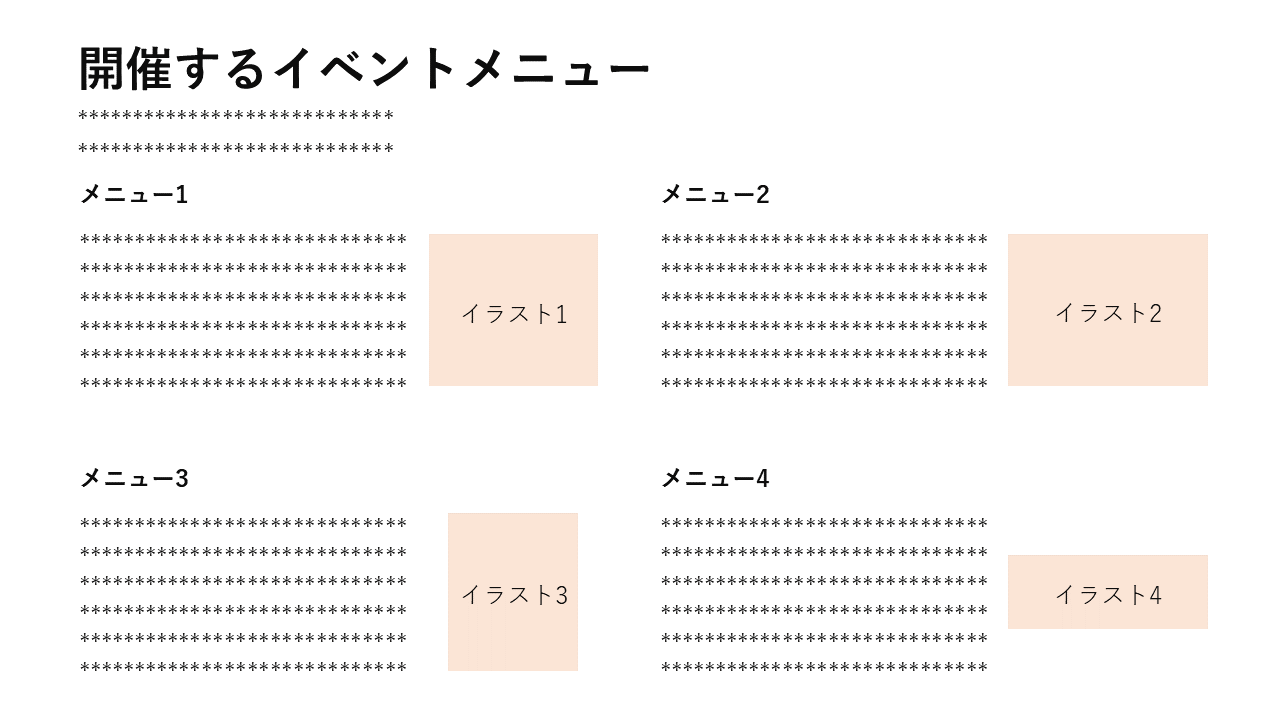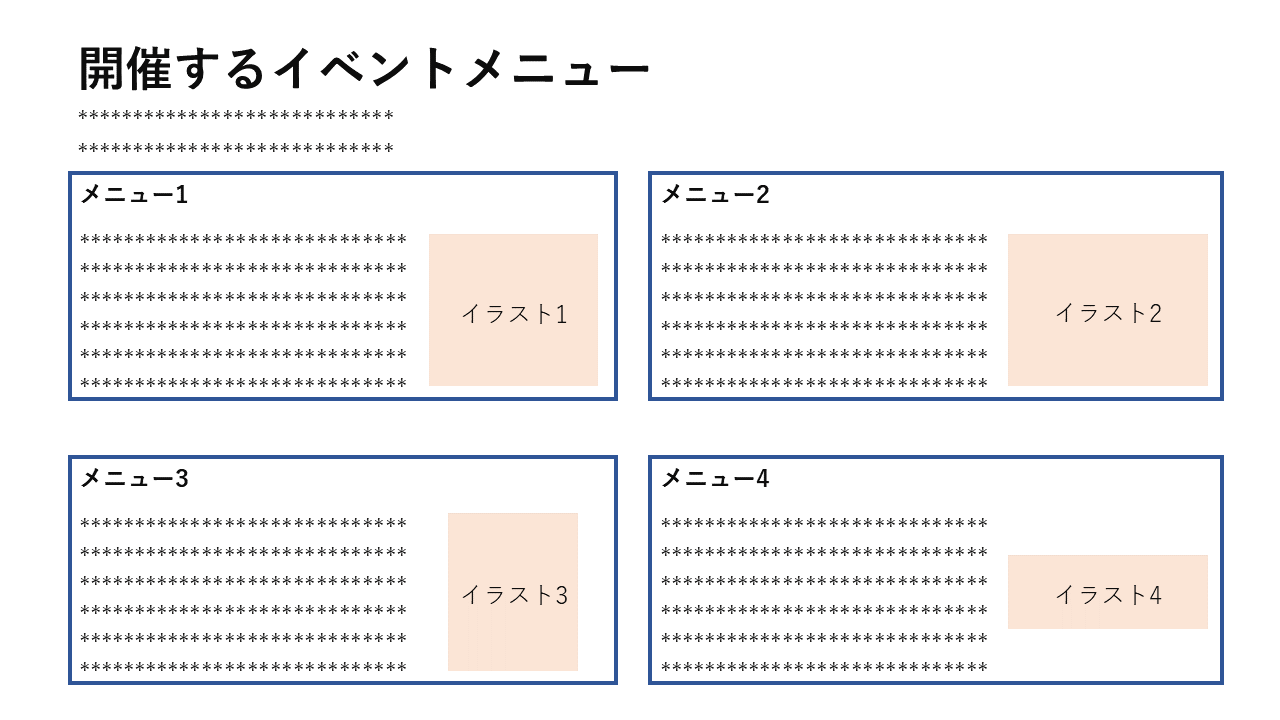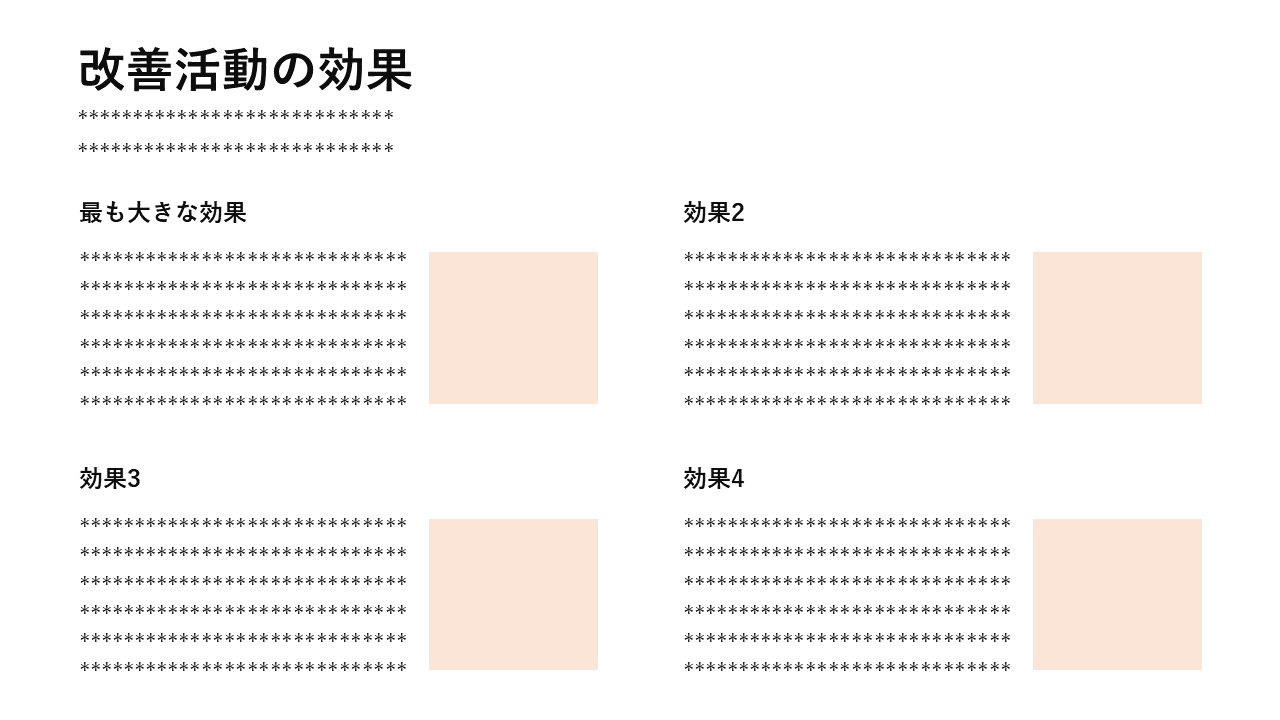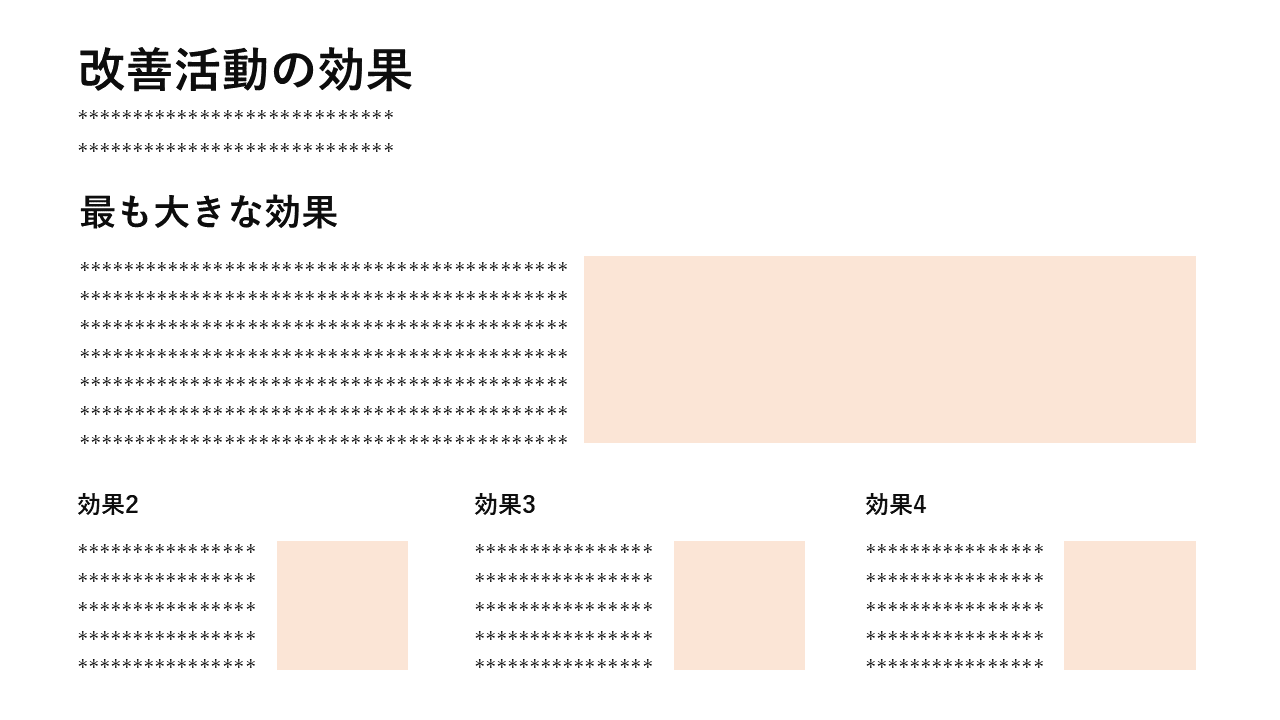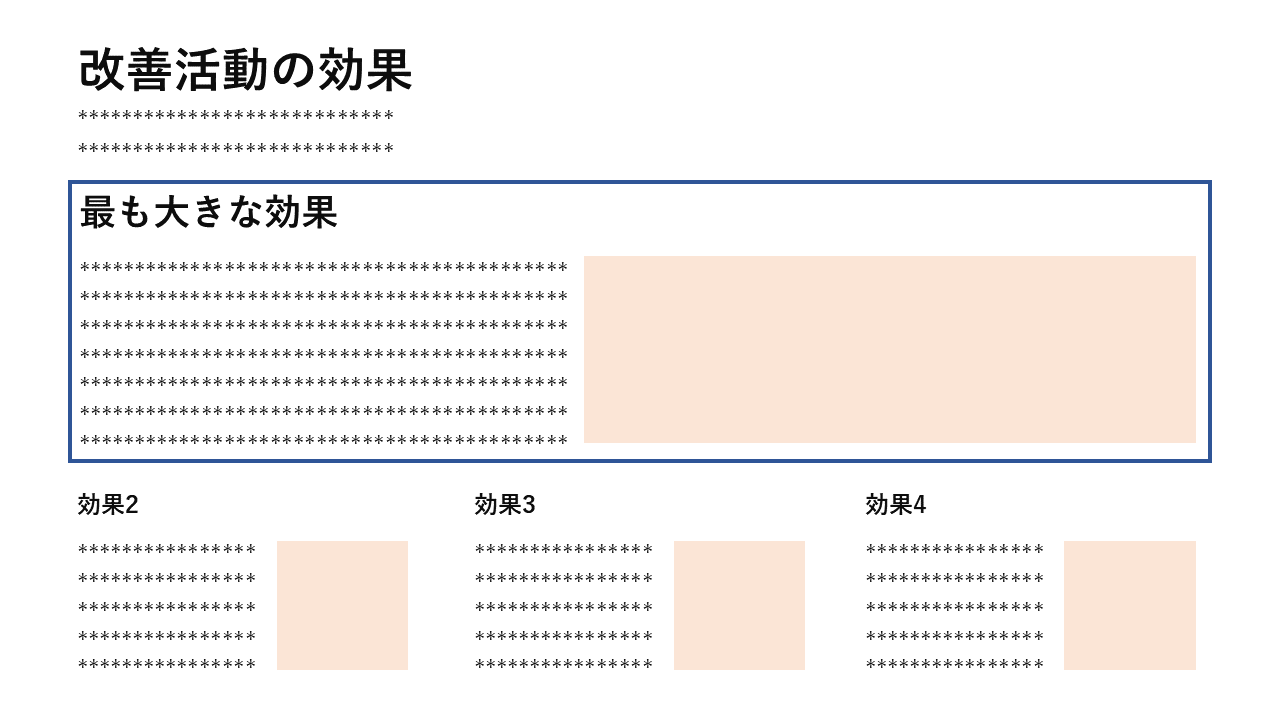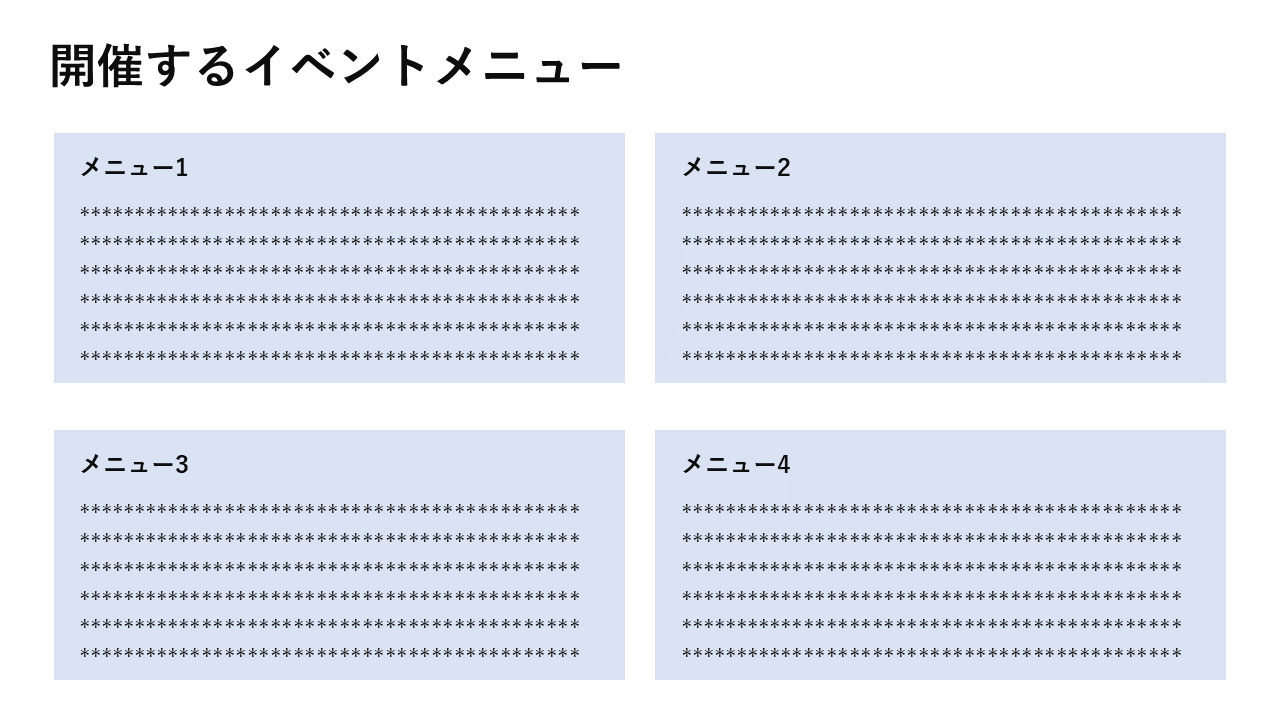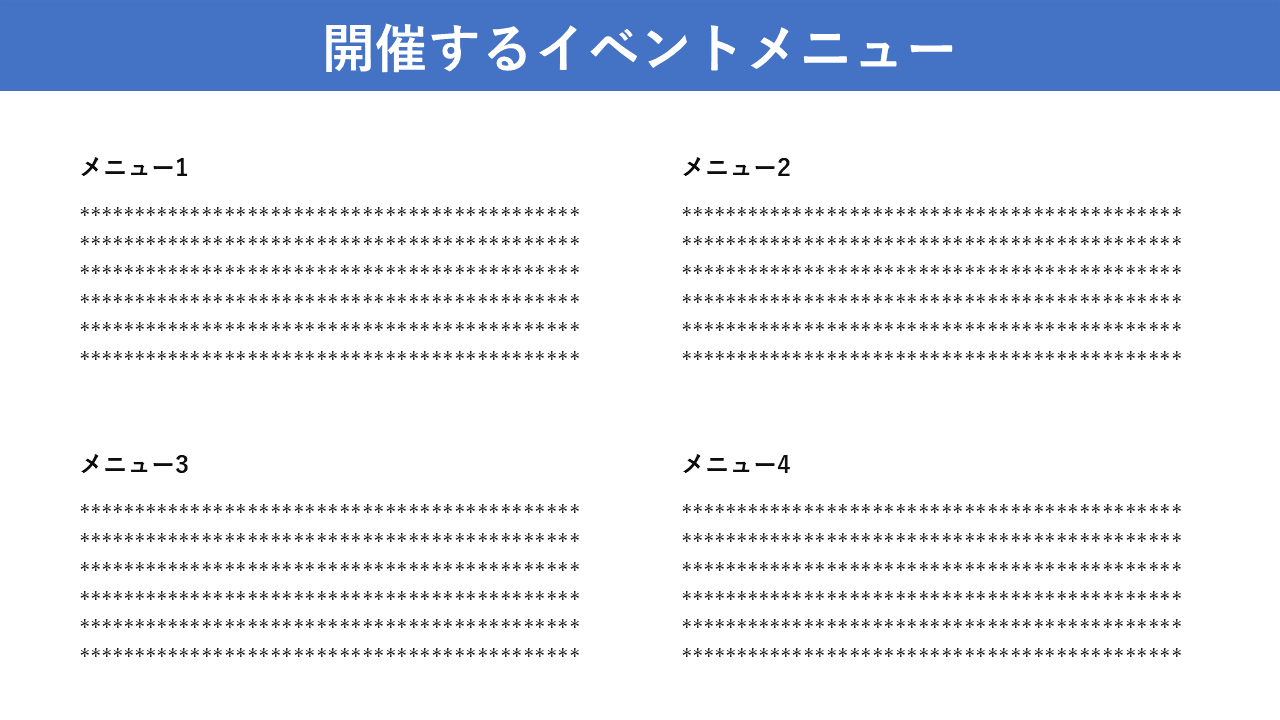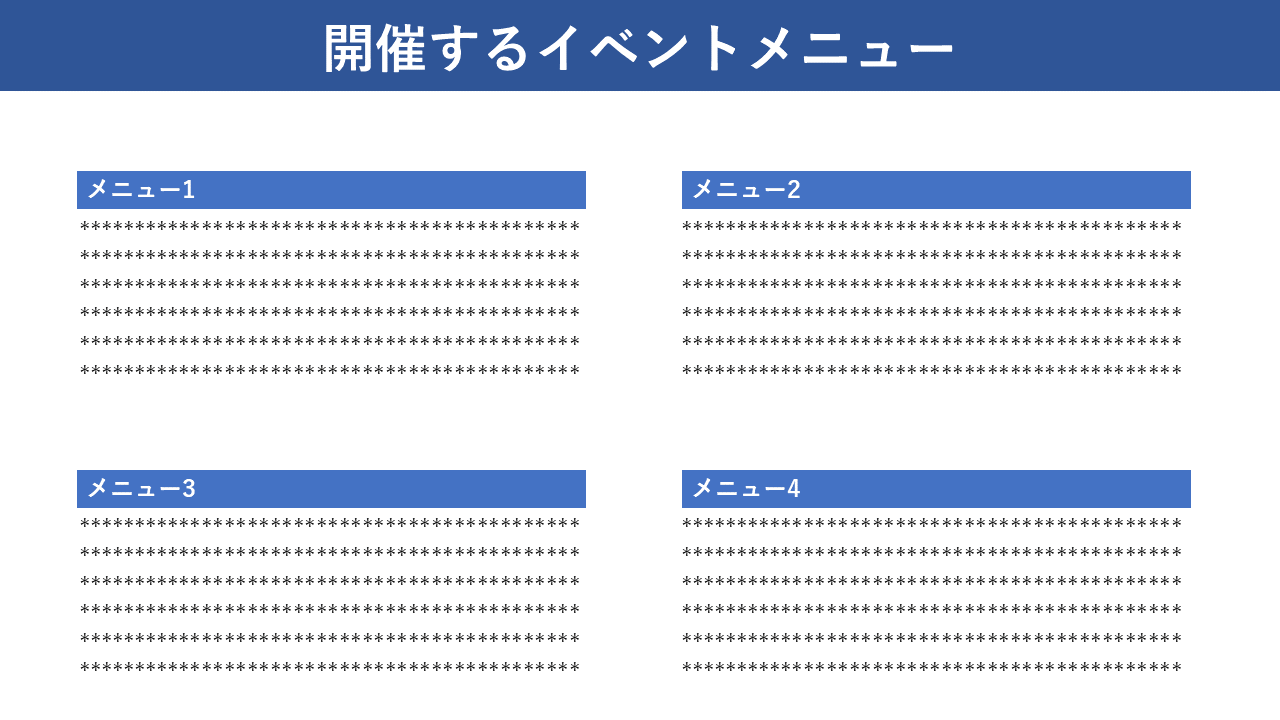会社での昇進や昇格の論文を書く際の、少しハイレベルな記述で合格を確実にするためのテクニックを、例文を用いてご紹介します。
まとめでは新しい要素を書かない
論文を書くときでも、長い文章や説明資料でも、「背景」や「前書き」に始まり、「詳細内容」を経て、「まとめ」へとつながります。
その「まとめ」では、それ以前に述べてきたことをまとめます。新しい理論の展開はしません。あくまで「まとめ」ですから、述べたことを簡潔に列挙して、主張を添える程度にします。
たとえば、「研修でのプレゼンの心得」の説明において、詳細内容のところで、
1. 最初のつかみが重要
2. 話し癖を控える
3. 話すスピードに緩急をつける
という、講師の振る舞いについて論理展開してきたケースを考えます。
この場合、「まとめ」の段階では、1~3の内容を簡潔にまとめます。「まとめ」の中では、以下のような要素は盛り込みません
「発表資料にも訴求力をもたせる」
「受講者の人数に制限を設ける」
「グループワークも取り入れる」
これらの要素が「まとめ」で新たに出てくると、聞いている人は混乱してしまいます。
このルールを守ると、全体的にまとまりのある流れの論文に整います。
内容に対して結論を飛躍させない
資料や論文を書く場合、最終的に主張する結論が、事前に用意されていることが多いです。その結論は、前提や詳細内容がしっかりと支えていなくてはなりません。内容に対して結論が飛躍してはいけない、ということになります。
「わが社が業界のイノベーター的存在になる」
というテーマ(結論)に沿って論文を書くケースを考えます。この結論に値する論文の内容で、
「社員一人ひとりがコストダウンと人材育成を今以上に意識して業務に取り組む」
ということを長々と書き、
「このコストダウン体制確立と人材育成風土の浸透により、わが社はイノベーター企業への変身を遂げる」
という流れになると、まったくつながりません。
たとえば、「イノベーター的存在になる」という結論に直接結び付るなら、
・常に新しい技術を発掘
・既存技術の応用
・従来にない取り組みの支援
・発明賞の強化
といった、かなりレベルの高い取り組みが前提となります。平社員がこのような取り組みを主導することはほとんどないと考えられます。自分の日常業務の小規模な取り組みに対して結論が飛躍しないように、うまくつなげる必要があります。
コストダウン活動を進める
⇒従来にない部品輸送でコストダウン推進
⇒商品の新たな物流モデルを確立
⇒他の会社がやっていないことで存在感
⇒学会発表や業界誌に投稿
⇒業界のイノベーター的存在を目指せる
多少の飛躍感は残りますが、コストダウン⇒イノベーターにつながりました。自分の取り組み内容を少しずつ結論へとつなげることで飛躍感が緩和されますので、論文テーマになりそうな結論を日頃の業務と結びつける練習をしましょう。
つなぎの言葉を工夫する
文章を書く際には、つなぎの言葉を工夫するとスムーズな流れを作ることができます。普通に文を並べただけだと、箇条書きのような響きに聞こえてしまいます。
「しかし」「または」くらいは、誰でも知っていますが、これだけでは昇格試験での論述を高度に展開していくには不十分です。
この項目では、つなぎの単語や表現で便利なものをいくつかご紹介します。以下の表現以外にもたくさんありますが、この程度の表現の使いこなしで、昇格試験論文は十分に書けます。
重ねる
また
そのうえ
さらに
しかも
重ねていうと
例
三案すべて実行した。さらに、第四案も考案した。
説明する
つまり
すなわち
要するに
詳しく解説すると
例
各担当者に細かく業務を割り振った。すなわち、各々がミッションをもって推進することになった。
例を挙げる
たとえば
例を挙げると
例
プレゼンには、さまざまな留意点がある。たとえば、結論を最初に話す、聴き手を惹き付ける、などである。
例える
例えていうと
例えるなら
例
設計業務をこなして経験値を積んでスキルアップした。例えていうと、スポーツのように実際に手足を動かして上達したようなものだ。
補足する
ちなみに
補足すると
加えていうと
例
すべて部門の創意工夫のみで達成した。ちなみにこれだけの短期間で実現したのも初めてのことだった。
比べる
これに対して
一方
これと比較して~は
例
国内生産での標準書は確立した。一方、海外拠点での運用は検討中であり、年度末までに完結させる予定である。
条件だしする
もし~なら
仮に~だとすると
例
仮にこの解決策が採用となれば、ランニングコストの増加は免れない。
別の選択肢を挙げる
または
あるいは
もしくは
これとは別で
例
これら三案の運用で各々検討を進めるか、あるいは、コスト面だけで一案に絞ってから進める。
逆転させる
しかし
しかしながら
それに反し
ところが
これとは逆に
例
最終的には第三案に決まった。しかしながら、品質面での懸念が残るため、引き続き検討を行う。
歩み寄る
もちろん
たしかに
とはいっても
例
商品のリリース日程には納得がいかない。たしかに品質とコストは素晴らしいが、やや開発期間が長いと感じる。
別テーマに移す
ところで
さて
それでは
本題に移すと
例
開催場所の調整が順調なことが確認できた。ところで、人員確保のほうが問題ないかというと、こちらはやや懸念が残っている状況だ。
理由付けする
なぜなら
その理由は
そのために
なぜかというと
例
新しいプロジェクトは、日程遅延が濃厚です。その理由は、致命的な品質問題が解決できないためです。
結論付ける
したがって
結果として
結論からいうと
例
新しいサービスが施行されました。したがって、従来サービスは全点撤収となります。
サラリーマン必携! 記者ハンドブックを活用して「書く」スキルアップ
繰り返しを避ける
昇格論文試験では、当然のことながら長文になります。単語、表現、内容共に繰り返しにならないような書き方をすることで、読み手を飽きさせずに、読み進めてもらうことができます。
単語や表現、文章、それぞれの繰り返し回避について解説します。
単語や表現の繰り返しを避ける
「です」「ます」「となっています」「と考えられます」など、たくさんの結びの表現がありますが、なるべく連続させないほうがよいでしょう。
また、同じ単語も連続させないほうがすっきりと読めます。
良くない例
その取り組みが中断することになりそうでした。十分な人員確保をできないことが原因でした。中断させないために、現状のリソースでの効率アップが必要でした。効率アップの結果、中断しないで取り組みを続行できました。
「でした」が連続していて、項目の列挙のように見えます。「中断」「効率アップ」も何度も使われています。繰り返し表現を避けて、文がきれいに流れるように工夫します。
良い例1
その取り組みが中断することになりそうだった。十分な人員確保をできなかったためである。現状のリソースでの効率アップが必要、ということになり、検討を重ねた結果、取り組みの続行が実現した。
良い例2
十分な人員確保をできないことが原因で、その取り組みの中断が懸念された。しかし、その対策として現リソースでの効率アップを図ることにより、続行できる結果となった。
例1、2、いずれも文末の表現を変えることで、項目の列挙の感じがなくなりました。単語の繰り返しもなくしましたが、十分意味の通る内容になっています。単純に表現を変えるだけでなく、言葉を削ることで、2文を1文にする工夫も必要です。
「Aということになった。理由はBだからであった。」
という文章を、
「Bのために、Aとなった。」
と書き換えるだけで、スッキリします。
コンパクトに文章をまとめる練習をしてみてください。
同じ文章の繰り返しを避ける
同じ意味をなす文章の繰り返しが多いと、全体的に冗長になり、中身が薄くなってしまいます。同じ意味をなす文章とは、簡単に書くと、以下のようなものです。
緑は私の好きな色です。
私の好きな色が緑です。
つまり、私は緑が好きです。
書き方はそれぞれ異なりますが、意味することは同じです。このような現象は、文の筆記の調子が乗ってきたり、強いアピールポイントを書いたりするときに発生しやすいので、注意が必要です。
ひとつ例を挙げます。
良くない例
本商品の前のバージョンでは、その形状での製造が困難であることが、製造段階で分かった。形状が実現困難だと判明したのが、製造段階だったということである。そのため、今回は商品企画の段階で、その商品の製造や運用が可能かどうか、関係部門で協議を行った。商品の製造可否と運用可能性の協議を、企画段階で行ったのである。
ダメ押しのように文が重ねられている、という感じです。単純に2つ目の文をそれぞれ削除すればOKです。
良い例
本商品の前のバージョンでは、その形状での製造が困難であることが、製造段階で分かった。そのため、今回は商品企画の段階で、その商品の製造や運用が可能かどうか、関係部門で協議を行った。
自分で書きながら、同じ内容の繰り返しになっていないか、1文1文確認しながら書き進めることをおすすめします。
まとめ
この記事では、
・まとめでは新しいことを書かない
・結論を飛躍させない
・つなぎの言葉を工夫する
・繰り返しを避ける
の4つをご紹介しました。
これらを論文に取り入れて書くことで、合格が確実なものへと近づきます。ぜひ、読み手を意識して練習してみてください。