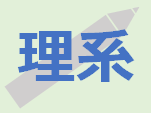就活している学生の中には、大企業に入りたいと思っている方が非常に多いです。中にはベンチャー企業や中堅企業に入って、若いうちから大きな仕事を任されて成長したい、という方もいるでしょうが、安定した高い給料や充実した福利厚生など、大企業ならではの恩恵を受けられることもあり、大企業はいつの年も人気です。ここでは、就職活動で、大企業に内定をもらうために必要な取り組みや学生の間にやっておくべきことを、大企業に内定をもらった経験のある筆者が解説します。
上位大学の方も、これを押さえておけば、大企業の内定をより確実なものにできるでしょう。
大企業と就活の現状
少しかたい話ですが、日本には株式会社が300万社以上あり、その中でいわゆる大企業と呼ばれる会社は、0.3%程度といわれます。自分が学生の中の上位0.3%に入ればよいかというと、そういうことではありませんが、大企業に入ることが難関であることは、一目瞭然です。
大企業は就活生に対して学歴フィルターを掛けている、とは近年よく言われます。上位の大学の学生だけ説明会に参加を優先させたり、実際の内定も上位校のみに集中させたりする採用方針です。学生を偏差値で判断するなどと、批判的な見方もある一方、これはやや理解する一面もあります。応募者が殺到する大企業では、まともに全ての学生を相手にしていたら、数人~数十人の採用担当者ではさばき切れないのです。上位大学に入った、ということは、
受験時代の限られた時間で、勉強計画、試験対策して高い結果を出した
ということとイコールで、上位大学に的を絞れば、会社に入ってからも努力して考えて結果をだしてくれるような学生に「当たる」可能性も高いのです。
大企業にも製造や事務、管理サポート業務など様々な業務があり、下位の大学出身者や高卒者もたくさんいます。しかしいわゆる上位の仕事である開発、研究、事業企画、営業、経営管理などの仕事をしている部門では圧倒的に上位大学出身者が多いのが現状です。
就活の現状から見ると、大企業が書類選考で通過させる判断になる大学のレベルは、会社にも依りますが、だいたいMARCHクラスまでです。その下の日東駒専クラスは、「優」ばっかりの成績上位の学生、更にその下のクラスの大学だと首席卒業レベル、といった感じです。実際に、大手企業にはMARCHクラス出身者はたくさんいます。早慶クラス出身者はもっといます。
就活の現場においても、早慶クラスの学生が大企業からの内定を数社もらっているのに対し、日東駒専学生が、応募した大企業をことごとく落ちているというのはよく見かけます。とはいえ、その中で日東駒専クラスやそれ以下の大学生でも大企業からの内定を得ている人が居ることは事実です。
2000年以降、世の中コンプライアンスの意識が高まり、昔のように簡単にコネ入社で大企業に入る、ということは少なくなりました。大企業は模範を示すべく、特にその傾向が少なくなりました。偏差値の高くない大学の学生はどのようにしたら、大企業の内定をもらうことが出来るのでしょうか?
大企業が学生に求めているもの
諸説あります。就職斡旋業者や大学の就職課、就職コンサルタントなど、大体それぞれいうことは多少異なることが多いです。
筆者が、大企業の入社試験を受けて、そして内定をもらったり落ちたり、実際に大企業で働いて、「大企業は学生のここを見ている」「大企業ではこういうスキルや視点がないとダメだ」と切に感じたことを挙げます。
大企業が中小企業と違うところは、何と言っても、その従業員数です。その会社単体だけでなく、グループ会社も含めて数万人とか数十万人、という規模のところも少なくありません。それはどういう事かというと、その数万人とか数十万人の従業員を同じ方向に向かせて、従えないといけません。従業員には奇抜なアイデアマンより、誠実で真面目でしっかりいうことを聞くタイプの人が求められます。
たくさんの従業員の中で仕事をする、ということは、一つの仕事を進めるうえで関係部門、関係者が多いということです。協調性が必要になります。また一人の仕事が大勢の人間に影響を与える、ということになりますから、筋違いな行動を取ってはいけません。限られた時間で機敏に理解し、多くのアウトプットを出せるような人が求められます。そのアウトプットを的確に出すためのベースとなるのは、「お勉強」の部分で、学生時代に学んだ専門分野の学識が必要です。あまり自己流ではなく、しっかり学問として裏付けのある知識です。そのような社員が圧倒的に多いため、同等のレベルで会話するためにも基礎学力の高さが求められます。
大きな会社は、国内、国外に関わらずたくさんの事業所、関連会社を持っています。どこに配属になるかは分かりませんし、出張や転勤も多いです。コツコツと狭い範囲で仕事をすることを望む人より、視野が広く自由度の効く、グローバル目線で物を見れる人を求めます。
大企業は中小企業と違って、会社の財政などがしっかりしている場合が多いです。これにより通常の業務以外で、様々な取り組みを実施することが多いです。直接会社の利益に結び付かないような取り組みに時間を割く余裕があるということです。どのような取り組みかというと、職場で今より働きやすくするための取り組み、とか、課員の士気を高める活動、有識者が集まっての新しいアイデア創出の会などです。もちろん小企業だって、会社としてこのような取り組みはしています。しかし、大企業ではこのような取り組みの数がものすごく多いのです。様々なアイデアを出して、積極的に新しい取り組みを出来る人が求められます。
大企業は従業員が多いこともあり、たくさんの人と関わる、と先に述べました。たとえ課長などにならなくても多くの後輩や関係者に仕事をしてもらうことが多々あります。リーダーシップが必要になります。たくさんの人に命令して動かす、ということではなくて、説明して目標を共有して、協力を仰ぎ、仕事を進める、というスキルが必要になります。協調性とはまた違ったスキルです。大企業なので、リーダーもたくさん必要です。この人は将来リーダーになってくれそうか、という目線で見られます。
■まとめると、
・真面目で誠実である
・基礎学力、専門分野の学識がある
・グローバルな視野を持っている
・アイデアを持って積極的に新しい取り組みが出来る
・リーダーシップを持っている
ということになります。これをうまくPR出来るように、学生時代に何をするべきか、次の項で詳しく解説します。
その前に、大企業ならでは、でなくどの会社でも必要なことも挙げておきます。
自己管理ができる人、とか、気遣いが出来る人などです。
自己管理ができる人とは、健康管理、仕事の管理、そして部下の管理や家族の管理にも延長していきます。仕事ができる人は、会議の時間に遅れたりせず、予定がダブルブッキングなどせず、肝心な日に突然休んだりせず、決められた日までにしっかり結果を出し、健康に気を付ける、ということが大抵出来ています。
気遣いが出来る人、とは自分の都合で人の仕事に割り込んだりしない、とか自分の余裕を見て課員のサポートに入ったり、など色々ありますが、まあ、就活でそういう要素が出て来ることはないでしょう。
学生の間に取り組むこと
先の項で挙げました、
■真面目で誠実である
■基礎学力、専門分野の学識がある
■グローバルな視野を持っている
■アイデアを持って積極的に新しい取り組みが出来る
■リーダーシップを持っている
について、具体的な取り組みを実際に行うべきであり、その結果を集約してエントリーシートや履歴書に記載したり、入社面接での話のネタにするのです。「別に面接官なんてこっちが何したか調べる訳じゃないからテキトーに書けばいんじゃね」って思うかも知れませんが、大企業の面接官をなめてはいけません。大企業の面接官たちは人を見るプロです。ウソをついている奴は一発で分かる、そうです。実体験であれば、どんな質問が来ても必ず答えられます。経験して、それに対してのありとあらゆる質問を予測し、全て押さえておきます。
具体的に見ていきましょう。学生の間に出来ることは基本的には限られていますから、
サークル、授業、試験、卒論、留学、ボランティア、アルバイト
あたりから材料を探していきます。普通に学生やっていて経験できるものから、時間とお金を掛けないと出来ないものまでありますが、時間とお金を掛けた経験のほうが他の就活生を差別化することが出来て、より有利に働きます。
求められるそれぞれの要素についての具体的な取り組みは以下になります。
就活生に差をつける5つの取り組み(勉強編)